29.喫茶店『ドラゴン』にて③
全身ずぶ濡れで帰ったらカッと目を見開いた紅葉に服を引っぺがされて風呂場に放り込まれ、すぐに熱いシャワーを浴びたものの、翌日、見事に熱を出した。「あー…」体温計を放り出す。まぁ、そりゃあ、そうか。馬鹿だなぁぼくも。ホントに……。
『自業自得です』
「厳しいね、奥さん…」
茶化したけど紅葉は無表情にぼくを見下ろしている。心なしか怒っているような…。機械にそんな心があるのなら、だけど。
雨の日に濡れて帰ってきたぼくが全面的に悪いのはわかっていたので「ハイ、すみませんでした」首を竦めて謝っておく。それで紅葉が納得したのかは謎だけどさっきよりは若干表情がやわらかい、だろうか。『お粥は口に入りそうですか』「タイ米かぁ。まぁ、しょうがない……頼んだぁ」『はい』紅葉には基本的に情報処理を任せているけど、家事炊事もできる。調理の場合味見はできないからあくまでレシピ通りとはなるけど、今はそれでもありがたい。
ぼんやりとしてはっきりしない頭で天井へと手を伸ばす。「コーヒー…」ノアが微笑みとともに差し出す白いカップが見えるようだ。
(コーヒー。飲みたいなぁ。うつしたら嫌だし、治るまでは行かないけど……)
小さなキッチンに立つ長い黒髪の後ろ姿を見ていると、ここが日本で、自分はどこにでもいる大学生とか社会人で、今日はたまたま体調を崩してしまってパートナーに看病されている…そんな妄想がぼんやりと頭を覆って、は、と吐息する。半分は呆れて。半分は諦めて。
この場所に来てから。飾らない自分として活動するようになってから、長年貼り付けていたKの顔が剥がれてきて、ぼくは少し焦っている、のかもしれない。このままじゃ誤魔化し続けて来た滝沢蛍としての自分ばかりが出てきそうで、それが怖い、のかもしれない。
できるだけ早くこの仕事を終えたい。
コーヒーの香りとアンティークな品物に囲まれた、ただ読書をできるあの平和な場所から、逃げたい。
ぼくには与えられることのない平穏に知らないフリをできるロンドンで、ぼくはずっと独りで立たなくてはならない。魔術師という魑魅魍魎が集う街で戦い続けなくてはならない。
本当は、そのことに、いい加減疲れてきている。……そういう自分がわかる。わかってしまう。
(この仕事を早く終わらせよう。戦いの日々に戻ろう。平穏に浸かって心が戦意喪失する前に……)

とくに体が強いわけでもなく体力があるわけでもないぼくは、ただの風邪を完治させるのにたっぷり三日かかった。
曇りのその日、いつもよりもこもこと厚着した格好で喫茶店ドラゴンに顔を出すと「いらっしゃいま…」せ、と言いかけたリリーがぼくを見るなりほっとした顔でカウンター奥でカップを磨くノアを振り返った。「ノア。いらっしゃいました」「、あ」顔を上げたノアがリリーと同じくどこか表情を緩めて「お見かけしないなと思ってて。よかった」と笑うから、人の優しさに三日ぶりに触れたぼくは、格好悪い笑い方しかできなかった。
そんな優しい笑い方をしないでほしい。好意を振りまかないでほしい。当たり前の顔をして、ぼくの孤独を癒さないでほしい。
「風邪を引いてしまって。治るのに時間がかかりました。あ、コーヒー、お願いします」
ノアは頷いて、見慣れた手順でコーヒーの準備を始めた。「最近また冷え込みましたから。あたたかくして眠ってくださいね」「はい。お腹出して寝てちゃ、だめですね」苦笑いするぼくにノアも緩く笑みを浮かべる。
いつもはキッチンの方にいるシリルが今日はタブレット片手に店の中に立っている。ぼくの方には来店時に一瞥をくれただけだが、彼が目に見える位置にいることに少しの緊張が生まれる。
あの日突然現れたぼくが問い質したこと……アーヴァイン・ブラッドはリリーだけでなく彼にも深く関係していることだ。Kという魔術師を彼は警戒しているはず。ぼくがそうだとバレないよう慎重に振舞わなくては。
リリーが不器用な笑顔で差し出したコーヒーを「ありがとうございます」と受け取って、白いカップの中の液体を一口すする。
うん。おいしい。と思う。
コーヒーの良し悪しなんてよくわからないままだけど、臥せっていた三日間、コーヒーが飲みたくて仕方がなかった。
一度は妥協してドリップのコーヒーを淹れてみたんだけど、やっぱりコレだ。ノアが淹れたコーヒーでないとおいしいと思えない。
じんわりと広がっていくあたたかさと苦みを味わっていると、シリルがぼくが座る窓際の席のすぐそばまでやってきた。ぼくを怪しんで……ではなく、窓のカーテンをつまんで調べている。新調を考えているんだろう、タブレットにはカーテンのオーダーページが表示されていた。
「ノア」
「うん?」
「色はどうする」
「どうしようか…。白が無難だと思うんだけど」
カウンターから出て来たノアがシリルのタブレットを覗き込んだ。二人で喫茶店のカーテンの買い替えについて吟味している、その横でコーヒーをすすりつつ、ぼくは紅葉の言葉を思い出している。
風邪がある程度治り、ようやく頭が回り始めたぼくに紅葉が教えたのは、シリルとノアが大学の同期の友人であるということ。彼らの間に魔術的な繋がりは一切なく、イギリス生まれイギリス育ちなのにも関わらずその外見から陰湿なイジメにあっていたノアをシリルが助け、そこから大学での友人関係がスタートする。
周囲からすればシリルは人やコミュニケーションの中心的人物であり、彼がいるから成り立つコミュニティやパーティーその他が多く存在していた。男女問わず人の間をもったり盛り上げたりする気分屋の彼がノアを擁護するのなら、周囲もそれに倣う…という部分があり、ノアは大学では比較的平穏な日々を過ごしたという。
一見すれば日本人風のノアとモテるイギリス人は結び付かないし、なぜシリルがノアをそこまで気にかけたのかは不明だけど、そこはそれ。
とにかくそんな経緯があり、現在の彼らはこうして喫茶店まで経営している、と。
変に緊張しないようひっそりと深呼吸をしたが、持ってきた文庫本を広げる気にはなれなかった。まだ病み上がりだし(病み上がりの胃にコーヒーもまぁよくないとは思うんだけど)、他のものを頼む気にもなれず、今日はコーヒーだけいただいて顔を出したってことで帰ることにした。
その日もチップ分を上乗せした代金を支払うと、ノアに「お大事になさってください」と心配そうな顔を向けられて言葉に詰まった。「また、来ます」なんとか笑った返したけど、顔色、まだ良くなかったろうか。確かにコーヒーを入れた胃はちょっとゴロゴロしているけどさ。
逃げるように。いや、喫茶店から逃げたぼくは、角を曲がって喫茶店からこちらの姿が見えなくなると病み上がりの体で走って借りているアパートに戻った。そのままベッドに飛び込んだぼくを紅葉が追ってくる。
『風邪がぶり返しましたか?』
「なんでもない。大丈夫」
頭まで布団を被ってこもった声で答え、あっちへ行けと手を振ると、紅葉は少しの間のあと寝室から出て行った。
ぼくは仕事でここにいる。『日本人の青年がテレワークで仕事をしつつ、あの喫茶店が気に入ったからこの田舎町に越してきた』という体でここにいる。
本当はそれは全部嘘で、ぼくは天才魔術師Kで、ウォッチャーから依頼された仕事を完遂するためにここに。
(何を参っているんだぼくは。こんなこと今まで腐るほどしてきたろう)
ノアが、リリーが、ぼくの姿を認めてほっと安心したような顔をした。その事実がちくちくと小さく胸を刺してくる。
………天才魔術師Kではなくて。なんの役にも立たない日本人の滝沢蛍でも。彼らはぼくを案じてくれるのだ。
ぐるりぐるりと廻り続ける思考は、やはり病み上がりだったのか。気付けば気を失うように寝ていて、目を覚ましたときには日が暮れていた。「…しまった」時間を無駄にした。ああもう。病み上がりっていうのはまともなことも考えられないのか。
紅葉が作ったお粥を食べ、まだぐるりぐるりと回転している思考を落ち着けるため、散歩に出ることにする。『お供します』「いいよ。悪目立ちする。あまり人の印象には残りたくない」イギリスの田舎町に日本人がいるだけで目立つのだ。男女で歩いていたらさらに目を惹く。それは避けたい。
ロンドンの大通りよりはずっと騒がしくない、電光掲示板の光もなければ立体映像の広告が踊るわけでもない砂利道を小石を蹴飛ばして歩く。
頭からつま先まで冷え込んだ空気に包まれることで、ぐるりぐるりと鈍い歯車のように鈍足で回転を続けていた思考が鋭く、冷たく、静かになっていく。
孤高の天才、魔術師K。実の親に売られたかわいそうな人間。ぼくはもう誰も信じない。利害の一致する関係だけがこの世のすべてだ。頼れるのはお金だけだ。裏切らないのは機械だけだ。ぼくは身をもってそれを知っている……。
(滝沢蛍。お前は戦場に生きて、戦場に死ぬ。それだけだ)
砂利道に沿って歩き、小さな教会を通り越して町の外れまできたとき、風の肌触りが変わるのがわかって足が止まった。
目の前には闇に沈んだ森の木々たち。空も黒に沈み、周囲にはポツンと一つ街灯があるのみ。
ヒュウ、と吹いた風に反射的にそばの茂みに飛び込んで身を隠す。
山と闇と空とが交わるそこから『何かがくる』と肌が感覚として告げている。
(参ったな。ここでは絶対に魔術は使わないと決めてるのに……)
茂みの中から目を凝らすぼくが見えているのか、いないのか。黒く混じり合った山と闇と空の境界からぬぅっとこちら側にやってきたのは青白い光を放ち浮遊する球体、あるいは火の玉だった。
ウィル・オー・ザ・ウィスプ、あるいはイグニス・ファトゥス。日本だと鬼火なんて呼ばれるモノがゆらゆら揺れながらこちらを目指している。
迷い出たのか、何かに引き寄せられたのか。墓場で見かけたらふっと消えるような類のモノだ。そこまで害もない…と思う。ロンドンでは墓場以外で見かけたことがないから断言はできないけど。
大した害はないだろうとはいえ、一般人が見たら度肝を抜かれるだろうし、ぼくという魔術師に気付いているのなら仕掛けてくる可能性はある。
聖水でも持っていれば魔術に頼らず対処ができたけど。あいにく、定期的に新しくしないとならない面倒な道具は持ち歩いていない。
さてどうすべきかと判断に迷っていると、青白く燃える球の上に影ができた。一振りのナイフを手にしたシリルが一切の迷いなく球体を一刀両断し、儚い光は音もなく灰のように散って消えていく。
彼の左目は駅のときのように仄かに光っていた。
もともと目つきのよくない彼だが、今は明らかに機嫌が悪いらしく、獲物を捜すように周囲を見回している。
ぼくは可能な限り心臓の鼓動を遅らせて息を止め、生体機能を忍ばせ、彼がぼくを見つけないことを祈った。ここで見つかるようなことがあればこれまでの苦労が台無しだ。
「シリル」
聞き覚えのある少女の声が彼を呼び、これもまた頭上から降ってきたのはリリーだった。赤いマントを揺らして地面に足をつけると「あちらは片付けました」と言う。
彼女は周囲になんの姿もないことを確かめると「あの…どうしてこう、色々と来るのでしょうか」そうこぼして首を傾げた。
シリルがイライラとした感じでナイフを放り投げると、それは当たり前のように消えてなくなる。「弱ってるからだよ、アレが」…アレ。とはなんだ?
「食べては眠ってを繰り返していますが、それでも回復はしていないのですか?」
「生きてるのが不思議なレベルだって緑のが言ってたろう。そのくらい今は弱ってる。普段吹けば消えるくらいに弱い有象無象が動くほどには弱ってるんだ。
だから守る必要がある。それがノアの望みだ」
リリーが神妙な顔で頷くと、シリルは彼女を連れて喫茶店のある方角へと砂利道を戻っていった。
可能な限り抑えていた生体機能でふっと大きく息を吸って、吐く。ああ、苦しかった。
今の会話を整理しよう。
ノアの喫茶店では何かが弱っていて、それをウィル・オー・ザ・ウィスプなどの存在が狙っている。
シリルの口ぶりを考えるに、夜になれば毎日のようにああいった存在が湧くのだろう。さっきのは定期的な見回りと駆除作業だったに違いない。
問題は『何』が弱っていて、それがノアや彼らとどう関わっているのか…。そこにあの翁は関係しているのか否か。
「はぁ」
茂みの中に座り込んで深く息を吐く。
今日も一つの情報を得たわけだけど、まだまだ、滝沢蛍としての活動は続きそうだな。頑張れ、ぼく。
リリーの祖父、アーヴァイン・ヴラッドに死ぬ一歩手前まで追い詰められてしまった金のドラゴンは現在も弱ったままであり、夜になると毎晩のように魔的なモノが湧き出しては彼女の力と命を自分のものにしようと狙っていたりします
ドラゴンを守ること=ノアの頼みでありノアのためである、という方程式なのでシリルは力を使えています。要は考え方次第( ˘ω˘ )
リリーは『自分(と祖父)のせいでこうなってしまった』という罪の意識もあり、自分にできることはしようと動いている感じ
1月は小説強化月間にしようと決めたので、まだまだ更新予定です
アリスの小説応援! にポチッとしてもらえると励みになります(ӦvӦ。)
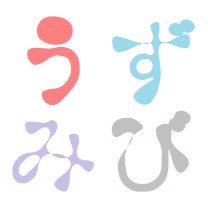






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません