27.喫茶店『ドラゴン』にて①
ウォッチャーご用達の指定の赤い電話ボックスに入り、駅を出てから電源を切っていた端末を再起動させる。
面倒な手順のアレやコレやを介してようやく連絡をつけたウォッチャーの顔である金髪碧眼の少女はまた一段とクマが目立つ顔でこちらの呼び出しに応じた。
『どうだい首尾は』
「そのことで報告があるんだけど、メールの方がいいかな」
『…いや。私も休憩がしたい。キングス・クロスの9¾番線で落ち合おう。このあと十二時でいいかな』
「りょーかい」
人気作品の9番線と10番線の間の柱にあるあのスポットを提示した彼女に一つ頷く。
9¾番線とは、平日でも休日でも観光客とファンで溢れている場所だ。姿をくらますにも会話を誤魔化すにも申し分ないだろう。
電話ボックスを出てキングス・クロス駅に向かう。
セント・パンクラス駅と隣り合っている、というか繋がっているキングス・クロス駅は、セント・パンクラス駅と比べると外観などが若干見劣りする煉瓦造りの建物だ。
老朽化により大幅な改装工事が行われ、外観のパッとしなさに比べて中が今風なモダンに仕上がっていること、暗いと不人気だった駅の裏手も再開発されたことで観光スポットとしても有名になった。
プラットフォームには有名作品の9¾番線を再現した場所もあり、おかげでキングス・クロス駅はいつも必要以上に人がいてうるさいったらない。
今日も今日とて、例のスポットには人が並び、マフラーを巻いて壁に半分突っ込んだ形のカートの持ち手を握って写真を撮ってもらう観光客で賑わっている。隣にあるショップもすごい混雑だ。
うるさいなーと思いつつぼんやり待っていると、「やぁ」と聞き憶えのある声がした。視線を落とすといつの間にか隣に金髪の彼女が立っている。「やぁ」挨拶を返してポケットからルーンを取り出すが、手で制された。「今日は私が」こちらの情報漏洩防止の策が気に入らないのか、彼女は自分が用意した手段で視覚的、聴覚的に私たち二人をこの空間から隔離する。
一回使い切りの水晶を手のひらで転がしながら、彼女が私を顎でしゃくる。話せ、と。はいはい。
視線は目の前の9¾番線にはしゃぐ観光客に固定しながら、何気ない会話をする感じで口を開く。
「調べたのはブラッド卿に魔術を学んだ一般市民だ。具体的には二名、まだ生存している者が見つかった。接触したよ」
「それで?」
「一名はド素人。呪われた腕を持ったままだったから切り離させた。モノなら私の知り合いの医師が保管してるから、興味があるなら早めに連絡するといい」
知り合いの医師の電話番号を記したメモを出すと、一応、という感じで彼女は用紙をつまんでコートのポケットにしまった。「もう一人は?」「うん。こちらが本命だね。シリル・キーツというんだけど、これを見てほしい」コンタクトレンズ型の情報端末で記録した先ほどの映像…セント・パンクラス駅で日本人風の青年、リリー・ブラッド、そしてシリル・キーツの三人が連れ立って歩いている様子を立体映像で表示すると、たいていのことには慣れている彼女も目を見張った。「これは……」「確認したけど、リリー・ブラッドで間違いない」フードを被って顔を隠している少女を拡大表示する。顔の造りは提供された写真の彼女と99パーセント一致。
携帯端末で録音しておいたシリル・キーツとの会話も流す。
みごとな金髪をつまんで口元を隠し、何か考えていた彼女は『アイツはもう何もしない。クソじじいに強要されてヤってただけなんだよ。手を出すな』ブツ、と録音が途切れると険しい目元でこちらを見上げる。
「どう思う?」
「…そうだなぁ」
最後、こちらを見据えたシリル・キーツの左目が魔眼に近しい何かだったこと。そして、こちらを始終警戒していた彼の様子…。
「ウソを言っているようには思わなかったけど、何か隠している、気はするかな」
アーヴァイン・ブラッドは死んだと彼は言った。具体的なことには触れず、ただ事実を告げるような淡々とした口調だった。「もう少し調べるとするなら、シリル・キーツの警戒を解かないといけない。それこそ、こちらの彼」ここまで話題にも上がらなかった日本人顔の青年を示す。「まだ名前もわからないけど、気さくな仲のようだし、彼に取り入る形にすればなんとかなるかもしれない」まだ全然何も調べてないから、あくまで可能性の話だけど。
彼女は立体映像を見つめて黙り込んだ。
一応、依頼された仕事には進展があったのだ。『ブラッド卿は死んでいる』『リリー・ブラッドは生きている』…片方には証拠の映像もある。仕事は進展したと言ってもいいだろう。これ以上調べるかどうかは依頼人の判断次第だ。
映像に記録したリリー・ブラッドが『赤の他人が魔術か何かで扮装した姿』という線もありえないわけではないけど、それを見抜けないほど私の腕は落ちていないと思うし。今日見た彼女はリリーで間違いない。
ふう、と息を吐くと、金髪の彼女は腕時計型端末をかざした。
「リリー・ブラッドの生死がハッキリ確認できたのは進展だ。
彼女はブラッド卿の良い手駒だった。便利な人形を卿が簡単に手離すはすがない…とするなら、ブラッド卿が死んでいる、という説にも頷ける。
可能なら卿についてのもう少し詳細な情報が欲しい。継続して調査してくれ」
彼女から追加で振り込まれたのは二千ポンド。
うん、充分。だいぶ口座があたたまって嬉しい限りだ。
「次の連絡は、少し時間がかかると思うよ。不自然でない形で時間をかけて接触しようと思っているから」
「構わないよ。Kが好きなように、君らしくやりたまえ」
「りょーかい」
それで仕事の話は終了し、彼女の手のひらにあった水晶にパキンとヒビが入った。それまでの静寂が嘘のようにどっと人の声と気配が溢れる。
用は済んだとばかりにさっさと歩き出した小さな背中に「ちゃんと寝るんだよー」と声をかけると、苦笑した顔でこちらを振り返った彼女がヒラリと手を振った。

アパートの部屋に戻った私は、ひとまずKとしての顔を取り、紅葉にシリル・キーツと親しく話をしている日本人顔の彼の行方を探させることにした。
ネットという日々増え続ける膨大なデータの海から、名前も素性もわからないたった一人の該当者を見つけ出せというのは至難の業だ。
手がかりと呼べるのは顔がわかる記録映像のみ。
それだけを頼りにたった一人を見つけ出すことなど人間にはまず到底無理だろう。できたとしても時間がかかりすぎる。が、紅葉のタスクをそれ一点に集中させればできないということはない。
…けど、ここ数日でかなり酷使してしまった。そろそろ休憩に電源を落とさないとならないか。
目的の彼を探してくれたら一度休ませよう。そう決めて、ベッドに横たわったままピクリとも動かず演算だけを続けている紅葉に冷却用のシートをかけた。
検索を命じて丸二日が経過しようとしていたその日の夜、それまで死んだように動かなかった紅葉がパチリと目を開けた。「お」座り心地の悪い椅子で適当にネットサーフィンしていたところから腰を浮かせる。どうやら何か進展があったようだ。
体を起こした紅葉が枕元のタブレットを手にして立体映像を出力した。「ん? …喫茶店、ドラゴン……?」公式ホームページらしく、イギリスの田舎町の写真と一緒にコーヒーやアップルパイが紹介されている。『古き良きアンティークな空間で自慢のコーヒーをどうぞ』…か。
ページの最後の方にオーナーであるらしい日本人顔の彼が映っていた。ノアというらしい。どう見ても日本人顔だがイギリス生まれイギリス育ちとなっている。
それにしたって大きな収穫だ。さすがAI。おかげで目的地も定まった。シリル・キーツとリリー・ブラッドはおそらくここにいる。
膨大な情報処理を続けてすっかりヒートしている紅葉の頭を撫でる。あっつ。
「ありがとう。すごく助かった。
しばらく電源を落としていいよ。あとはこっちで進めるから」
『しかし……』
「紅葉。休みなさい」
命令すると、紅葉は渋々という感じでまたベッドに横になり、休止モードに入った。
…うん。これで私はまた床で寝ないとならないわけか。辛いな。ソファくらい買おうかな。
新しい冷却シートを持ってきて紅葉に被せながら、ホームページの上から下まで、すべての項目に目を通す。適当なアカウントを作ってインスタもフォローしておく。
投稿内容は新しいメニューの宣伝や本日のコーヒーと言ったものばかりで、本当に普通に店をやっているみたいだった。魔術の世界にどっぷり浸かっている二人と親しいのに、カフェ、かぁ。
善は急げとも言うので、私はフリーの何でも屋魔術師Kとしてではなく、日本人の滝沢蛍として、飾らない自分でセント・パンクラス駅から列車に乗り込んだ。
列車はあっという間にロンドンの街並みを通り過ぎ、見える景色は農園や田舎町の風景ばかりになっていく。
午前中に列車に乗ったのに、目的の無人駅に降りた頃にはすっかりお昼時になっていた。
ロンドンから遠出をすることがあまりないせいか、立体映像の広告が一つもない無人駅というのが物珍しい。田舎町らしく紙の広告が貼り付けられている掲示板には目的の喫茶店ドラゴンの案内もある。
件の喫茶店は今日も営業中だ。昼食がてら、様子見に行こう。
普段は作っている『フリーの何でも屋魔術師K』という仮面を脱ぎ捨てたぼくは、オンオフで自分を切り替えている。シリル・キーツと接触したのはほんの数分間。背丈こそ同じだが、顔も声も違う。まず私がぼくと見破られることはないだろう。
イギリスの田舎町らしい、三角屋根のこじんまりとした煉瓦造りの家が続く風景を歩いていくと、道に古風な看板が出ていた。昔の絵本に出てきそうな手作り感溢れるドラゴン姿の看板。あれだ。
ホームページを見たから店の内観はわかっているけど、開けっ放しになっているカフェ内に一歩踏み込んで、実際よりもキラキラとした店内に息を呑んだ。
骨董品と呼んでもいいくらい古いブラウン管のテレビが奇跡的に映像を映し、ノイズが混じったサッカー中継の音が響く店内には様々なものがあった。壁には古い何かの地図。チェアとテーブル一つ一つに年季が入っており、魔具として使えそうなモノまである。
こういうゴミゴミした古い感じ、わりと好きなんだよなぁ。
思考が趣味と魔術に傾倒しそうだった自分を制して、ただの滝沢蛍として「こんにちは」と細い声をかけると、白いカップをキレイにしていた少女が顔を上げた。リリー・ブラッドだ。「いらっしゃいませっ」慌てたようにこちらにやってきてぼくが一人なのを確認し、奥の座席へと案内する。
彼女は血術を使う魔術師のはずだが、黒いエプロンをつけて、接客して、普通に店員として働いているようだった。
「ご注文はお決まりですか?」
「本日のコーヒーと…キッシュと、プレーンのスコーンを。ください」
「はい」
リリーは不慣れそうな笑顔を浮かべてパッと身を翻す。
ぼくは持ってきた日本語の文庫本を取り出した。
ぼくの設定としてはこうだ。『滝沢蛍はロンドンに馴染めず、ある日たまたま日本人顔の店主が経営するカフェの存在を知り、そこを訪れる』こちらはカフェを訪れた理由。『滝沢蛍はカフェで文庫本を一冊読み終えるまでのんびりするのが趣味である』こちらはカフェで滞在する理由だ。
もう何度となく目を通したお気に入りの文庫本なら、読んでいるフリをして店内を観察することもできる。
横目で見る限り、店主である日本人顔の彼がコーヒーを淹れ、奥のキッチンではスコーンとキッシュが用意されているようだ。カウンター奥の空間にチラリとシリル・キーツの姿が見える。どうやら彼も普段は店を手伝っているらしい。
「どうぞ」
トレイでコーヒーとキッシュ、スコーンを持ってきたリリーの笑顔はまだ不慣れさが滲んでいた。なので、ぼくも同じような笑みを返して、本に栞をはさんでコーヒーをいただくことにする。
……うん。普通においしいんじゃないだろうか。いや、よくわからないけど。コーヒーなんてどこで飲んでも同じだと思っているし。まぁでも水っぽくてしゃびしゃびで飲めたものじゃないってことはないかな。
お腹が空いていたのでキッシュの方にも手をつけたけど、こちらもなかなか、どうして、おいしいじゃないか。スーパーのものよりおいしいぞ。
スコーンはイギリスらしい形をしているし、食感もいい感じ。このジャムおいしいなぁ。
つい普通にもぐもぐ食べてしまってからハッとする。
いやいや、しっかりしてくれぼく。シリル・キーツとリリー・ブラッドの観察に、店主のノアに取り入るのがしばらくの仕事なんだから。
ずず、とコーヒーをすすりながら、再び文庫本を広げる。
店内は他に老夫婦が一組いるだけで、喫茶店はすごく賑わっているというふうでもない。この田舎町には他にカフェも少なくて、だから利用している、という感じか。
文庫本を斜め読みしながら確認したところ、テイクアウトでキッシュやスコーン、アップルパイが売れていくけど、店内に留まって食べる人はあまり多くない印象だった。
文庫本を半分読んだあたりでコーヒーのおかわりをお願いして、その日は文庫本を一冊読み終わるまで喫茶店に滞在した。
チップ代込みで代金を支払い、「またいらしてください」と笑顔を浮かべるノアにぺこっと頭を下げて店を出る。
(…他愛のない話をできる間柄になろうと思うなら、常連客にでもなるしかないか)
今日観察していた感じだと、ノアが店内に一人になるということはかなり少なかった。リリーかシリルのどちらかが一緒にいる。彼と自然に仲良くなるには、常連客として話ができるようになるほかない、か。
そうなると、ここにアパートでも借りるかなぁ。そうすれば店以外でも接触する機会がありそうだ。
口座の金額には問題がないわけだし、部屋ならすぐに借りられるだろう。なんならウォッチャーの力を借りてもいいかもしれない。
とりあえず、今日のところはロンドンのアパートに戻ろう。紅葉のクールダウンぐあいも気になるし、引っ越すなら手続きもあるし。
天才魔術師Kの本名は滝沢蛍(たきざわほたる)という元日本人で、色々あって現在はイギリス住まいのフリー魔術師として生きています
彼のお話ものちのちね
アリスの小説応援! にポチッとしてもらえると励みになります(ӦvӦ。)
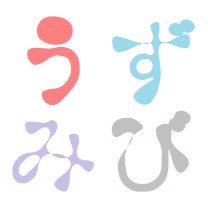






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません