28.喫茶店『ドラゴン』にて②
AIであり雑事その他をしてくれる紅葉のことは『奥さん』ということにして、件の『喫茶店ドラゴン』のある田舎町にアパートを借り、必要最低限のものを持って移り住んで二週間がたった。
二、三日に一度のペースでカフェに足を運び、小説を一冊読むまで滞在する日もあれば、パイやキッシュをテイクアウトだけしていく日も作り、ぼく滝沢蛍は『最近越してきました』という顔で喫茶店ドラゴンに出入りをしている。
「いらっしゃいませ」
顔を出し続けたかいあって、ぼくを見ると店主であるノアが笑顔を向けてくれるようになった。それはたぶん、ぼくが自分と似ているアジア人顔だから、というのもあるのだろう。
「こんにちは。今日はよく、降りますね」
入り口でなるべく雨粒を払って、敷いてあるマットで念入りに靴の裏を拭ってから店内に入る。「そうですね。庭に水やりをしなくていいのは助かるんですけど…」そういえば、庭先には家庭菜園のような畑があったっけ。
雨で客足が遠のくことを見越してか、店内にシリルとリリーの姿はない。今はぼくと彼だけのようだ。
これはチャンスだ。ようやく訪れたチャンスとも言える。
いつもなら店の奥に引っ込んで店内を観察するところを、今日はカウンター席に座った。ここなら話がしやすい。
「コーヒーをお願いします」
「はい」
ノアが豆からコーヒーを淹れる準備をするのを眺めながら、何気ない話から脱線するなよ、と自分に言い聞かせて一石を投じる。「ここは、長いんですか?」「お店自体はまぁまぁ長いです。僕が継いでからはまだ一年と少しですけど」「いつもの、お二人は?」「ああ…」今はここにいない二人がいるだろう場所を見るように、彼は店舗の二階部分を見上げる。
「女の子の方は、最近働き始めたばかりです。接客業はしたことがないみたいで、不慣れな部分もあると思いますが、一生懸命やってくれています」
なるほど、と頷く。リリー・ブラッドはこれまで観察してきたとおり、魔術のことなんて忘れたふうに普通に真面目に働いている、と。「では、彼の方は? 少し目つきがキツい感じの」つい本音がこぼれたが、これはノアも思っていることのようで苦笑いしている。
「すみません、悪気はないと思うんですけど…。彼は大学時代の友人で、色々あって、店を手伝ってくれています」
「友人ですか。いいですね」
大学時代の友人。そこから調べればノアという彼のことももう少しわかるかもしれない。これは収穫だ。
やかんを火にかけたノアが首を傾げた。「お仕事は、こちらで?」無難な話題として振られるだろうネタだ。当然そう訊かれたときの返事は決めてある。
「ぼくは在宅ワークが可能なので、わりと自由が利くんです。このカフェが気に入って……どうせならと、近くに越してきたんですよ」
無難なことを言ったつもりだったけど、彼はそうは受け取らなかったようだ。ぽかんと気の抜けた顔をしている。
(何かマズいことを言ったかな)
不自然ではないよう気をつけたつもりだったけど。
内心どぎまぎしていると「そう言っていただけると…とても、嬉しいです」ありがとうございます、と笑った彼はなんだか泣きそうだった。ああ、この地でやっていくのに苦労しているんだろうなというのがその笑顔から滲み出ていた。
ふと、ここには仕事できていて、君たちから情報を聞き出そうとしているだけなんだ…なんてことは知られたくないな、と思った。
できればすべてが穏便に運んで、ぼくは知りたい情報を持って、仕事の都合で引っ越すことになりました、とこの町を去れるといい。それが理想だ。誰も傷つかない。傷つけない。だけどそういう無難な選択に限って叶わないってことをぼくは知っている……。

コーヒーを飲んだあとはスコーンをあるだけテイクアウトさせてもらい、チップ代に色をつけて「お釣りはいいです。じゃあ、また来ます」と頭を上げて喫茶店を出て、傘立てに一本だけ入っている自分の青い傘を広げる。
一度に根掘り葉掘りと色々なことを聞くのは愚策だ。自然に、何度かにわけて、世間話の延長線として今後もこういった何気ない話をしていこう。
傘を揺らしながらのろのろ歩いてアパートに戻ると、紅葉が待っていた。『おかえりなさいませ』「ただいま」表向き、紅葉はぼくの妻、ということになっているので、あまりおざなりな対応にならないよう気をつけつつ部屋の扉を閉めて、一息。
「今日は進展があったよ。例の喫茶店の店主、ノアだけど、シリル・キーツとは大学の友人だったらしい」
『調べます』
「頼むよ」
人間のぼくがやっても時間ばかりがかかるから、情報関係は紅葉に一任している。
ソファに腰かけて情報処理を始めた紅葉から視線を外し、テイクアウトしてきたスコーンを安物のトースターであたため一口かじる。
店で出される食べ物のだいたいはシリル・キーツのお手製らしい。
彼が料理どころかケーキなどのスイーツも手がけているとは。人は見かけによらないなぁ。
スコーンを一つ食べ終わって、ソファで目を閉じたまま微動だにしない紅葉を眺める。
情報をまとめるにはそれなりに時間がかかるだろう。紅葉のことだから当時の大学の様子やら出来事やらも遡って調べてまとめるのだろうし。
「買い物に行ってくる。いい加減野菜を食べないと調子が悪いし」
しばらく喫茶店のテイクアウトの品だけで暮らしていたけど、日本人故か、ぼくは野菜が食べたくなる方なのだ。
ソファで情報検索に処理力のほとんどを費やしている紅葉は目だけこちらに向けた。『お気をつけていってらっしゃいませ』「うん」再び傘を手にして部屋を出る。
それに、喫茶店にばかり通う金持ち、とご近所さんに誤解されるのも面倒だし。生活感のあることもしておかないと。
この田舎町で一番大きいスーパーでカートを押しながら適当に野菜やチーズを突っ込んだりしていると、見知ったブロンドヘアを見つけた。リリー・ブラッドだ。今日は買い出しを任されたのか、手にしているメモを度々見ながらカートを押している。
こちらから声をかけるとさすがに馴れ馴れしいか? 変な警戒をされても困るしなぁ…なんて考えつつ、気付かないフリで黙々と商品をカートに突っ込んでいると、「あ」と声。しゃがんで水のボトルを持ち上げたところから顔を上げる。リリーがぼくに気付いたらしく、ぺこり、と頭を下げてくる。
「常連さんの」
「こんにちは。買い出しですか?」
今気付いた、やぁどうも、という感じでへこっと頭を下げる。彼女ももう一回ぺこっと頭を下げて「はい。今日はわたしの当番で」カートを振り返ってメモと中身を見比べる彼女は一生懸命のようだった。おそらく、こんなことにも慣れていないのだろう。長くアーヴァイン・ブラッドに人形として扱われていたのだ。知っていることに限りがあり、年相応の少女としての経験は浅いに違いない。
水のボトルをカートの下の段に並べて立ち上がる。ああ重い。力仕事は慣れてない。そんなもの魔術で…そう、魔術でできていたから。ここではその片鱗も見せることはできない。シリルやリリーにぼくって人間が魔術師であることを悟られないにはそうするしかないのだ。
「あの」
意を決した、という表情で口を開いたリリーが「ありがとうございます。喫茶店に、通ってくださって」それで言うことがそれだから、なんとなくいたたまれない気持ちになる。
ぼくがあの喫茶店に通うのは仕事でしていることであって、仕事内容を完遂したらぼくはロンドンに取って返す…と思う。ふと気紛れで足を伸ばすことはあるかもしれないけど、ここはロンドンからまぁまぁ離れているし、仕事が終わったあとも通うかと言われると……答えはノーだ。
なんともいえない苦い気持ちが口の中にじわりと広がったのを堪えて笑顔を浮かべる。「コーヒーも、食べ物も、おいしいお店ですよね」「はいっ」リリーは勢いよく頷いた。目がキラキラしている。そうしていると彼女はどこにでもいるただの少女のようだ。
「わたし、ノアに助けてもらったんです」
「彼に?」
「はい。優しくしてもらいました。わたしには、そんな資格はなかったのに。
だから、今度はわたしが彼のためになりたくて、お店を手伝っているんです」
「そうでしたか」
助けてもらった、優しくしてもらった、というのはおそらく彼女の祖父であるアーヴァイン・ブラッドの件を指しているんだろうが……具体的な話が気になるなぁ。それがわかればぼくの仕事は終わりなのにな。
(焦るな)
気が急いて妙なことを言ったら台無しだ。
焦るな。資金はある。時間をかけろ。
「彼とは、こう、顔立ちのせいか、とても親近感を感じていて……ぼくも友達になれるといいんですが」
はは、と笑って口にする、これはまぁ半分は本当だ。あの日本人顔に親近感を感じている。友達は……よくわからない。思えば、ぼくって友達、いなかったし。
ぐるぐると回る思考がなんだか嫌なところに落ちたのを感じる。「じゃあ、ぼくは仕事が待ってるので、これで」リリーに頭を下げてカートを押し足早にレジに向かうぼくは、半ば逃げるようだったと思う。
これじゃあ不自然だろう。馬鹿かぼくは。
背負ってきたリュックに水やらの重いものを詰めれるだけ詰め込み、エコバッグにもパンパンに物を入れて、地面を踏みしめるようにしながらアパートまでの道のりを歩いた。
なんとなく濡れたい気分だったので傘はスーパーに置いていった。どうせ安物だ。盗られたってかまいやしない。
ぽたぽたと髪から雫が落ちる。濡れた髪が額にはりついてとても邪魔だ。
………あの喫茶店で働く三人は、魔術の世界にいなくてもそれなりに充実した日々を送っているように見えた。
ぼくも。素質がない家に突如として生まれた天才児でなければ。魔術なんて知らない世界に生きていれば。平凡な家で、両親のいる生活で、友達と遊んでゲームしたり、恋をしたり、高校ではっちゃけたり、大学生で就活したり、していたんだろうか。
叶わないことだ。思っても仕方がないことだ。ぼくは金に目が眩んだ両親に売り飛ばされたのだから。誰に習わなくとも使える様々な魔術の才に恵まれて産まれてしまったのだから。
(でも。もし。叶うのならば)
喫茶店ドラゴンで過ごす穏やかな時間の流れの中に、ぼくの居場所があれば。そんな夢が叶えばいいのに。
滝沢蛍、イギリスではKと名乗っている彼は日本で生まれましたが、魔術師でもない家系に生まれた天才でした
その血筋でもないのに突如として生まれた魔術師、それも天才ということで、彼には億単位の価値がつき、結果、イギリスの魔術師の家系に売り飛ばされてしまいます
もしも『意図的に』魔術の天才を生み出せるのなら?
魔術師たちの思惑により買い取られた彼は様々な実験や薬を試され、人間不信に陥り、現在のような『一匹狼』『どこにも所属しないフリーの何でも屋』『パートナーはAI』というスタイルで落ち着いたというわけです
そんなわけなので、K、滝沢蛍は人を信じていませんし、お金と機械だけが自分を裏切らないと思っていますが、心の奥底では人としての平穏な生活を望んでいたり、信じられる人間に出会いたい、と思っていたりするのです
そんな彼にちょっと重荷となっている今回の潜入調査。果たしてどうなるのか…?
アリスの小説応援! にポチッとしてもらえると励みになります(ӦvӦ。)
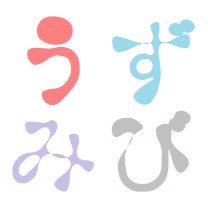






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません