14.道端の百合
店内の掃除を終え、空気を入れ替え、アンティークなテレビの電源を入れる。
ノイズ混じりの音を聞きながら開店の準備をしていると、携帯端末が着信を知らせて仮想ウィンドウを立ち上げた。懐かしいようなベルの呼び出し音が鳴る。
相手は、おじいちゃんのときからお世話になっている、コーヒー豆の仕入れに行く店。
不思議に思いながらコール音に応じて……その内容に少し驚いた。あまり入荷されない有機の豆が手に入ったというのだ。
「買い出しぃ? わざわざ豆をか」
通話を終えた僕に、呆れ顔のシリルが面倒くさそうな顔でコートを放り投げてくる。
キャッチして羽織りながら「イイ感じのが入ったんだって、電話までくれたから」と返して硬貨の入った財布をポケットに突っ込んだ。
顔を出します、と返して店の扉にクローズの看板をかけたのがついさっき。
本当に買うかどうかは試飲して決めるけど、あのおじさんがオススメまでしてくれるのは珍しいことだ。
コーヒー豆は温暖化の影響で栽培できる地域が減り、希少価値が上がっている。そんな環境下で有機で育てられた豆といったら、安くはないだろう。それでも足を運ぶ価値はある。
バナナを皮ごと食べている金色の竜に事情を説明し、「行ってきます。おいしかったら、買って帰ってきますね」『いってらっしゃい』子猫サイズがもとの猫くらいの大きさに戻った彼女は、今日もよく食べ、よく眠る。それが回復のコツらしい。
シリルと連れ立って、今日も今日とて人気のない駅に行き、ロンドン行きの電車を待っていると……駅のホームの端っこに、茶色いコートを着て蹲っている人を見つけた。
浮浪者の姿は珍しくない。駅から駅を渡り歩いて路銀を稼ぐ人もいる。でも…。
手元で何かのグラフと数字を睨みつけていたシリルが僕の視線を追いかけた。そしてタブレットに視線を戻すと「別に珍しいもんでもないだろう」と、浮浪者のことをそう言う。
確かに、シリルの言うとおりなんだけど。
そのコートの人物は、僕らがロンドンから帰ってきたときにも同じ場所で蹲っていた。「……おい」一歩踏み出した僕にシリルが棘のある声を出す。
構わずフードを深く被ったコートの人の前にしゃがみ込んで、持ってきた財布に少しあった硬貨を差し出すと、相手がのろりとした動作で顔を上げた。
コートを着て蹲っていたのは、まだ十代と思われる女の子だった。
澱んだ緑の瞳をした彼女は、僕が差し出した硬貨は受け取らず…ただ、僕を見て、目を大きく見開いて硬直した。
「えっと…」
一方僕は、コート以外何も着ていない彼女に穴が開くほど見つめられて、視線に困った。
まさかこんな、無人の駅で、人を誘っている女の子がいるなんて誰が想像するだろうか? 僕はしてなかった。だから、これは路銀のつもりで…。買うとか、そういう意味ではなくて。
とにかく、寒そうだったので、前を隠すという意味でも、自分のマフラーを外して彼女にかけた。「おいノア」トゲトゲしたシリルの声が背中に刺さる。いい加減にしろ、と暗に言っている。
…シリルに止められても。マフラーをかけた僕の手を強く掴んで俯く少女を放っておくことは、僕にはできそうにない。

イギリスは紳士の国だ、と、未だに言えるのかは謎だ。でも、駅で裸同然の女の子を見つけたのなら、保護するのは、紳士でなくとも大人として当然だと思う。
もう陽が暮れる。コート一枚で過ごせるほど、英国の夜はあたたかくない。
「今晩の寝床と、ご飯くらいは出してあげられるよ」
「………」
「僕はノア。君は?」
黙りこくっている少女がちらりと窺うように僕を見た。目が合うとすぐに顔を俯けて、消えそうな声で「リリー」呟く声音で名前を教えてくれた。
彼女はリリーというらしい。
なるべく彼女を安心させようと、僕らの後ろで顰め面をして歩いているシリルのことも説明してみる。「あっちの彼はシリル。僕の友達」「………」リリーはシリルのことが怖いのか、彼のことは見ようとはしなかった。
裸足の彼女を気遣って、なるべくゆっくり、舗装された道を選んで歩く。
自宅兼店舗である喫茶店ドラゴンに戻って、「ただいま」と声をかけて店内に入ってから気付く。もし彼女がドラゴンの姿のままでいたら、と。
幸い、金色の彼女の姿はなかった。二階で眠っているのかもしれない。
シリルは迷わずキッチンの方に入っていくと、今日の買い出し品を放り込み始めた。「コーヒー豆はテーブルでいいよ」一応声をかけておく。わかっているだろうけど。
思えば、大人の男二人を前に、少女が委縮するのは当たり前だった。僕がどれだけやわらかく接したとして、彼女の警戒や緊張が解けるのは難しいだろう。
キッチン兼リビングである空間で立ち尽くしている彼女に椅子を勧め、片付けをしているシリルと、自分と、リリー。三人分の紅茶を淹れることにする。
理由は、豆の砕く音が、今の彼女には刺激が強いかもしれないと思ったから。
それに、紅茶の方が簡単に入る。お湯を沸かしてポットに注いで待つだけだから、外気で冷えているだろう彼女には、すぐにあたたかい飲み物をあげたい。
「はい、どうぞ」
しっかり抽出した琥珀色の液体の入ったカップをリリーの前に置く。
砂糖とミルクも好きなだけ使っていいよ、と前に置くと、彼女は恐る恐る手を伸ばして角砂糖を二つ、ミルクをたっぷりと入れると、カップに口をつけた。
相変わらずの顰め面で、角砂糖を三つも入れた紅茶をすすっていたシリルが嘆息して二階を指した。「なんかあったら呼べ」「わかった」紅茶を飲み干したシリルは自分の荷物を持ってさっさと二階に上がっていった。
僕と二人になって、少し、彼女の緊張が緩んだのを感じる。
「お腹は空いてる? 簡単なものでいいなら作るよ」
「……でも…」
コートの上から自分のお腹を押さえた彼女がちらりと僕を見上げた。どうやらお腹は空いてるようだ。
冷蔵庫からベーコンと卵を取り出してフライパンでベーコンエッグに。切り分けたパンにはバターを塗って、焼いたベーコンエッグにチーズをのせて、完成。
トースターであたためたベーコンエッグパンを置くと、リリーはじっとパンを見つめた。「……、」意を決したような面持ちで、ようやくパンに手を伸ばす。
僕は調理の片付けをなるべくゆっくりしながら、彼女がパンを食べるのに専念できるようにした。
(…それにしても)
こんな片田舎で、あんな無人の駅で、商売をする子がいるとは。
ロンドンだというのなら、まだわかる。わかってしまう。
けれど、ここは田舎だ。客を取るにしても路銀をねだるにしても適さない場所。そんな場所でどうして…。
なるべくゆっくり洗い物をしてキッチンを片付けると、リリーはすっかりベーコンエッグパンを食べ終えていた。紅茶も空になっている。「もう一杯淹れようか」「で、でも…」「僕ももう一杯飲もうと思っていたんだよ。ついでだ」「…それなら…お言葉に、甘えて……」こくりと頷いた彼女に、二人分の紅茶を用意する。
二杯目の紅茶を飲み干した彼女は、カップを置くと、テーブルに額をぶつける勢いで頭を下げた。「ありがとう。ございました」「どういたしまして」なるべくやわらかい笑顔を浮かべて笑うと、リリーは若干表情を緩めた。
見ず知らずの家でシャワーを借りる、というのは女の子からすれば大変なことだろうから、あえて勧めず、お腹を満たして落ち着いたろうリリーを二階の空き部屋に案内した。
半分くらい片付けた部屋は、古いソファ以外は段ボールで埋まっている。
「ここなら貸せるんだけど。大丈夫そう?」
「野宿より、全然。大丈夫です。ありがとうございます」
僕の着替えと古い毛布を抱きしめたリリーがぺこりと頭を下げる。
最後にお手洗いの位置を教えて、頭を下げているリリーに手を振ってパタンと扉を閉めた。
ふぅ、と静かに息を吐いて、シリルと共同使用している自室に戻る。
シリルはソファベッドの上で胡坐をかいて、また何かのグラフと数字を追いかけていた。
「…怒ってる?」
口を開こうとしない彼に声をかけると、はぁ、とこれ見よがしに溜息を吐かれた。「怒るっていうよりは呆れてる、だな」「でも、さ。あのままにはしておけないよ」「なんで」「なんでって……」仮想ウィンドウをいくつも立ち上げている彼は、いらないものを指で弾いて消しながら、何か数字を入力している。
「ロンドン行けばいくらでも見るだろう。浮浪者も、物乞いも、身売りも」
「…そうだけど………」
「それとも何か。お前は見かけた不遇な人間を片っ端から救うのか? そんな財力も度量もないだろうが」
シリルは手厳しい。そして、その言葉は正しい。
……僕は、僕の手の届く場所にいたリリーの、力になれそうだと思ったから、そうした。今晩だけでもお腹を満たして、あたたかくして眠ってほしいと思ったから。それは心からの善意のつもりだった。
だけど、少し見方を変えるだけで、その善意は薄情な自己満足に変わる。
僕はリリーと名乗ったあの女の子をずっとこうして保護できるわけじゃない。ずっとご飯を用意できるわけじゃないし、あたたかい寝床を提供できるわけじゃない。
シリルの言いたいことは、わかる。解るけれど。
「だけどさ、シリル。
確かに在るものを、見てない、知らないって蓋をして忘れてしまうのは、かなしいと思うな」
在るものに、見ないことを選ぶ。
在るものに、知らないでいることを選ぶ。
その選択は、そうすれば自分は責任を負わなくてすむし、楽だろう。
(僕が虐められるのを、多くの生徒が見て見ぬフリをしていたように。僕が泣いているのを、多くの人が、知らないフリをしたように)
多くの人のその選択が僕には悲しかった。
たくさんの人が、僕のことを見なかったことにし、僕の涙はなかったことになった。
だけど、ただ一人、シリル・キーツという人間は、僕を陰湿なイジメから救い出すことを選んだ。
「あのとき、君は知らないフリをしないで、僕の手を取ったじゃないか。僕も同じことをしただけだよ」
本当は正義感のある彼は苦い顔をして舌打ちした。その頃のことを思い出したのか、口を歪めて仮想ウィンドウを睨んでいる。
その日はそれ以上の話はなく、彼は寝ると言って早々に布団を被ってしまったので、電気を消した。
そうするとやっぱりやることはないので、僕も大人しくベッドに入って、枕元で眠り続けている金の竜を横に目を閉じた。
14話め! ドラゴンってつくけどドラゴンの出番が控えめ!(
金のドラゴンさんは充電期間です( ˘ω˘ ) 寝る子は育つ!
応援! にポチッとしてもらえると励みになります❤(ӦvӦ。)
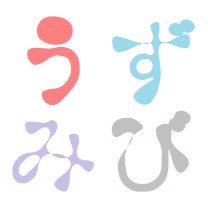





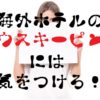
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません