8.まるで映画のワンシーン
かくして、現代の地図には載っていない、僕にとっては未知の登山へと挑む日がやってきた。
携帯端末で現在地を確認する。
……うん。ここは平野だ。羊や牛が放牧され、牧歌的な風景が密かな人気だったりする平野。端末の情報は現在地をそう説明する。
ここまでやってくる途中も、竜である彼女が言うような山は見えなかった。やっぱり平野だった。
だけど、彼女が人の姿になり、細い指先を掲げて空中に何かを描くと、平野の風景はぐにゃりと傾いだ。常識が崩れ落ちるように、水に絵の具を溶かすように、見ている景色は、簡単に歪んだ。
歪み続ける景色に目眩を覚えて、平衡感覚を失いそうになって。たまらずに瞬きして、次に見たものは、平野ではなくて森だった。
手にしている携帯端末は変わらずにここが平野であると示し続ける。でも。
「ここが……地図にない山…」
僕の目の前には、森が、広がっていた。
一本一本が立派で、とても背が高い木々。腰まで高さのある草花が自由奔放に、鬱蒼と生い茂る。イマドキでは珍しい、手付かずの自然だ。
道らしい道のない森を前に圧倒されていると、人の姿の彼女が白いワンピースを揺らして一歩目を踏み出した。
そうすると、不思議なことに、あれだけ鬱蒼と草が生い茂っていたのに、彼女の足元には地面の色が見えた。まるで植物が自分の意志で生える場所を彼女に譲ったような、そんなふうにも見えた。薄暗くて、陽の光の入らない森が、彼女を歓迎している…。
金糸の髪が揺れて、彼女が僕を振り返る。「ノア」「あ、はい」すっかり足も思考も止まっていたから、彼女を追った。
追いついた僕に彼女は言う。「人だけでは、永遠に森を出られません。私から、離れないように」「…はい」ゆっくりと頷く。
………永遠。彼女の口からそんな幻のような言葉を聞くと、本当のことのように思えてくる。
物語の中にいた竜が実際に存在した。幻だったはずの生き物が実際に生きていた。
それならもう、何が本当で、何が幻なのか。簡単に決めつけることなんてできない。僕が思っていた『当たり前』の現実は、彼女と出会ったことで崩壊した。
有限の時間の対義語の永遠だって、本当に、存在するかもしれないのだ。この森は、そういう場所なんだ。

彼女が歩けば草原が頭を垂れるようにその背丈を低くし、彼女の訪れを歓迎するように、歩く道を花が飾る。
背の高い木々の間からは木漏れ日すらこぼれなくて、森はひたすら薄暗かったけれど、幸い、彼女は道がわかるようだった。
白いワンピースに揺れる金糸の髪。とても登山をする格好ではない彼女。けれど、足取り軽く、気持ちのいい風の吹く草原を歩くように、彼女は軽やかだ。
けれど、その足取りも一時間もすると少し重くなってきた。
「…どうかしたんですか?」
僕の足で追い抜いてしまうくらいゆっくりとした歩みになった彼女の横顔を覗き込んで、ぎょっとした。顔色が悪い。紫色だ。唇なんて白い。
彼女は目を閉じると、小さな金色の竜の姿に戻った。まるで子猫くらいのその小ささに僕はさらにぎょっとしてしまう。「あれ…こんな、急に……?」猫くらいの大きさがあったはずなのに、金色の竜は、今では両手にのってしまうくらいに小さい。
呪いのせいで体が小さくなっていると言っていた。だけど、今朝店で眠っていたときはいつもの大きさだった。どうして急に。
飛ぶのが辛いのか、僕の頭の肩に乗った小さな竜は、辛そうに目を閉じて頭を垂れた。
『何者かが…呪いの、儀式を、進めています』
「え、」
『時間が、ないようです。このままいけば、私は』
消滅するでしょう。彼女はそうこぼして、小さな手の爪で前方を指した。『まっすぐ、行ってください。ノア。足元に、加護がなくなりますが、頑張って』「…、はい」彼女が先に歩くことで草原は頭を垂れるように背丈を低くして地面すら見せていた。けれど、それは相手が彼女であったから。ただの人間である僕に植物は遠慮も寛容も抱かないだろう。
革の手袋をギュッとはめ直して、片手で草をかき分け、もう片手で登山用のステッキで足元をつついて確認しながら進む。
もともとこうやって進むつもりだった。大丈夫。知識は頭に入れた。イメトレもしてきた。大丈夫。
そうやって、とにかく歩いた。薄暗い森を。自分の息遣いと、肩に乗る僅かな重みだけを感じながら。次第に重くなる足で、重くなる空気で、時折指示をくれる竜の言葉に従って、とにかく前へと歩いた。
目指すのは山頂。そこに彼女を呪い続けている何かがあるという。
……無心、というのは、こういうことを言うんだろう。
目の前の薄暗い森、その気配。自分と肩に乗る竜。それ以外に思うものがない時間。
ひんやりしている森でも、歩き続ければ汗も滲んでくる。
岩と砂ばかりで足場の悪い急斜面を登り、沼地のようにぬかるんだ地面を使い捨ての靴カッパを履いて通過した。登山初心者にはなかなか厳しい道ばかりだ。
(余計なことを考えなくてすむのが、スポーツの良いところだと、シリルは言っていたっけ。目の前のことを考えるだけでいい時間だ、って)
ふとそんなことを考えて、懐かしいような、そうでもないような学生生活を思い出して口元で少しだけ笑ったとき、目の前が急に開けて視界を光が差した。眩しい。
何度か瞬きして、光に慣らしながら目を開けて……。
どうしてかそこにシリルがいた。ついさっき思い浮かべた彼がいた。
程よく着崩したシャツにベスト。派手めなクラッシュ加工がされているジーパンにスニーカー。白地に黒いアクセントのペドラ帽子。
「シリル…?」
どうして、こんなところに。
僕がそう口にする前に、彼は流れる動作でポケットから手を抜いた。その手には旧式のリボルバー拳銃。狙いは、僕の左肩の、竜。
古い型の拳銃を持つ彼。
発砲音。
まるで映画のワンシーンのように遠くて、現実味のない音が曇り空へと吸い込まれて消えていく。
とっさに竜をかばって体を反転させた僕の右肩を熱いものがかすめていった。「…っ」今では片手に乗るくらいに小さくなってしまった竜をパーカーの胸元に押し込む。『ノア、』「しっ」理由はわからないけど、シリルの狙いは金色の竜だ。だから、あなたは隠れていて。
痛む肩に手をやりながら振り返る。
シリルは感情のいっさいを削ぎ落としたような無の表情でこちらを見ていた。その表情は僕の知る感情豊かな彼らしくなくて、思わず訊いていた。
「シリル・キーツ。君なのか…?」
「ああ。そうだな。お前の知らないオレだ」
そう言ったシリルは冷たい目で自分の背後を一瞥した。つられてそちらに視線をやる。そこには……おそらく、アレが、竜を呪っている場所。そう思える石でできた祭壇があった。中央には竜を象ったような人形。
すっかりくすんでまるで焼けたように黒く変色している人形の、無事な部分は、顔だけだった。それも首からだんだんと黒に塗りつぶされていっている。
アレが呪いの元凶だと、言われなくても、肌で感じた。
僕はアレをどうにかしなくちゃいけない。
だけど、誰が想像した? こんな場所に、まさか、旧友がいるなんて。つい最近再会したばかりの彼がいるなんて。
僕が祭壇から視線を剥がせずにいると、彼は薄く笑った。それは、自嘲気味な笑い方だった。昔、女にフラれたからやけ酒に付き合えよ、とパブを連れ回されたときに彼が見せた笑い方に似ていた。
「因果だなぁ。ロンドンでは偶然の再会……なんて思って、軽い気持ちで付き合ったんだけどな。まさかここにお前が来るとは」
薄い笑みを消すと、シリルは再び僕に銃口を向ける。正しくは、僕が隠した竜に。
「ドラゴンを出せ、ノア。オレの目的はソレだ。お前に用はない。おとなしく置いてけば、昔のよしみで、お前は見なかったことにしてやる」
半年ぶりくらいの更新となりました…。すでに忘れられてそう(´・ω・`)
応援! にポチッとしてもらえると励みになります❤(ӦvӦ。)
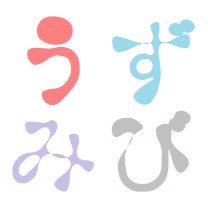






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません