34.You hear the crowds
ヴー、ヴー。
枕元に置いた端末が目覚ましとして振動する音と震えで目を覚まして、まだ眠いと訴える目をこすりながら起き上がる。「おはよ…」シリルは僕の目覚ましが鳴る前から起きていたのか、部屋着であるジャージ上下から白いシャツと黒いパンツ姿にとっくに着替えていて、シャッとカーテンを開けて部屋に朝陽を取り入れるとジャージの上着を掴んで「朝飯作る」と先に階下に下りていった。
まだ寝起きの頭ではゆっくりとしか動けず、緩慢な動きでスウェットの寝間着から着替え、白いシャツと黒いパンツ、カフェでの仕事スタイルに着替えて上からカーディガンを羽織る。
「おはようございます」
カゴの中で眠っている金色の竜に声をかけると、彼女は薄く目を開けて僕を見上げた。「コーヒー、あとで持ってきますね」まだまだ本調子とはいえない彼女の枕元には、いつでも食べられるようにとバナナが置いてあるけど、朝のコーヒーも欠かせない習慣だ。『今日は、ミルクを、たっぷり…お願いします』まだ眠そうに目を閉じた彼女の言葉に頷いてから部屋を出る。
階段を下りて顔を洗い、キッチンに入ると、シリルが朝ご飯にベーコンと卵を挟んだホットサンドをトースターに入れ、作り置きの野菜のスープをあたため直していた。
僕はその横でコーヒーを淹れる準備をする。
すっかり慣れてしまった朝の風景。少し前まで考えられなかった、一人以外の時間。
キッチンの小さな窓から見える外の景色には、久しぶりに感じる青い空がある。「今日は良い天気だね」一人じゃないことも手伝って、思わずそんな陽気な言葉もこぼれるというものだ。たとえ返事がなくても、シリルは軽く肩を竦めて反応はくれる。それでいい。満足だ。
携帯端末で今日の天気を表示すると、晴れ時々曇り。
今日は晴れ間に恵まれるらしい。最近は朝晩冷え込むようになってきたから陽射しはありがたい。洗濯もしないと。
「おはようございます」
声に顔を向けると、僕らと同じく白いシャツ、膝丈の黒いスカート姿のリリーがキッチンの入り口で頭を下げていた。そろそろここに住み始めて一ヶ月になるのに、未だに少し他人行儀というか。
僕はそんな彼女になるべく優しく笑いかけることにしている。
「おはようリリー」
「あの、わたしは、やることは」
「もうできる。座ってろ」
ホットサンドとあたためたスープがテーブルに並び、飲み物として僕の淹れたコーヒーを置く。「ちょっと、彼女に持って行くね」あたためたミルクをたっぷり注いだカップを持って「先に食べてて」と言うと、リリーは待っていて、シリルはさっさと食事を終えている。そんな風景にも慣れた。
食事のあとはシリルが後片付けをして、僕とリリーが店の開店に向けた準備をする。
まだ少し早いかなという気もしたけど、目で見てもあたたかいし、今日から暖炉の火を入れようか。

自分は世間や世界のことをあまりに知らないので、勉強がしたい。
そう言い出したリリーに、スーパーでの買い物の仕方や、教会という場所のことや、駅というもの、その利用方法など、身の回りにあって教えられることを順番にやってきて、この小さな町では教えられることがなくなってしまった。「うーん…今日はどうしようか?」お客さんが来るまではリリーに何かを教えるのが最近の僕の日課なのだけど、とくに思いつかない。今日は何を勉強しようか……。
学生時代の教科書でもあればよかったんだけど、専用の端末をレンタルしていたから、返却した今は残っていないし。
シリルに助けを求める視線を送ったけど、彼はスコーンの型抜き作業中だ。声をかけて邪魔をしちゃいけない。
BGM代わりにいつもつけている古いブラウン管のテレビは、今日もザラザラとノイズ混じりの音でニュース番組を流していた。CMに入り、ロンドンの大英博物館の建物を映す。
ロンドンの博物館といえば一番に思い浮かぶ、観光名所としても有名な場所だ。
リリーがじっとテレビを見つめた。
ギリシャの神殿のような姿をしている建物は、現代とはかけ離れているし、興味もわくだろう。
「あれは、なんですか? ハクブツカン、とは」
「一言で言うと、色々なものが展示されている場所、かな。世界でも珍しいものもあれば、歴史を語る遺物もあるし、本当に、色々あるんだ」
大英博物館は基本が無料だから、暇を持て余したときは僕もよく遊びに行った。
あそこは観光名所でもあるから、東洋人顔の僕がいても浮かない場所でもあったし。僕がいても許容される場所で、学生の財布にも優しい場所。自然と足が向くことも多かったな。
CMが終わったあともリリーがテレビを見つめていたので、ポケットにある端末で大英博物館を立体映像として出力して表示させた。
最近端末やタブレットの使い方も憶えてきたらしいリリーは、「どうぞ」と差し出す僕にぺこっと頭を下げてから端末を受け取って操作を始めた。表情以上に博物館に興味があるみたいで、あっちこっち表示させている。
(…喫茶店の経営は、昔より軌道に乗ってるとはいえ、満足なお給料を上げられる状態ではないし。リリー本人は『お世話になっているからお金はいらない』っていうけど、そういうわけにもいかない……)
大英博物館のエジプト部門の空間を隅から隅まで熱心に見つめる彼女を見ていて、一つ、いい考えが思い浮かんだ。
リリーのためにもなるし、現状満足なお給料を払ってあげることもできないことへのお詫びに、彼女を大英博物館へ連れていってあげよう。
善は急げ、なんて言葉が日本にはあるらしい。
善いことはためらわずすぐ行え、みたいな意味らしいから、これだ、と思ったら迷わず行け、ってコト、なんだと思う。
その言葉に従うわけではないけど、リリーは一生懸命喫茶店を手伝ってくれているし、僕も、たまには羽を伸ばしてもらいたいとも思うわけで……。
そんなこんなで、次の日はお店は休みにして、シリルを説得して三人で大英博物館までやってきた。
テレビのCMでも見た大英博物館は、古代ギリシャの神殿を彷彿とさせる、ロンドンという現代にあって異彩を放つ外観をしている。学生時代に来ていたときのままだ。
「これが、大英博物館…!」
緑の瞳を大きくさせてぽかんと口を開けているリリーが僕の腕を引っぱった。「はやく、中に行きたいです」「そうだね。行こうか。…シリル?」彼はといえば、とても退屈そうな顔で博物館を眺めていた。彼はこういったことには興味がないのだ。ならついてくる必要はなかったと思うんだけど、彼曰く『そういうわけにはいかない』らしい。その言葉の意味は、よくわからない。
シリルは溜息を吐きつつも僕らの後ろを歩いた。別行動をするつもりはない、と。
せっかくなので入り口の左手にあるデスクでガイドブックを購入してリリーに渡した。カラーの館内マップも買っておく。
イマドキ紙の地図なんて、と思うかもしれないけど、有名な観光場所では立体映像の使用は非推奨とされている都合上、仕方のないことだ。(そうしないと観光客が表示するマップだけで空間が埋まってしまう)
立体映像を処理する機能のあるゴーグルやコンタクトの類を使用して回る以外、この場所は紙のマップと床に定期的にある館内案内図を参照することを求めている。
「一日で回りきるのは難しいから、行きたいところを絞った方がいいよ。
今日回れなかったところはまた今度来よう」
「はい」
リリーがカラーのマップを手にまず行きたがったのは、端末で熱心に眺めていたエジプト部門だった。大英博物館を代表する石ともいわれるロゼッタストーンと呼ばれる石がある展示室だ。それ以外にも、イギリスでは見かけることがない守護神像や彫刻など、多くのものが展示されている。
リリーが忙しなく展示物に顔を向けるのに対し、シリルは何にも目を向けず、退屈そうな顔で携帯端末をタップしている。「……あのさ、別行動でいいよ?」と言うと睨まれた。なんでだ。
「変な感じがしたらすぐに言えよ」
「変な感じ? 何それ」
「なんでもいい。異変を感じたら言え」
シリルはそれきり端末に視線を落としてしまったので、僕は閉口して周囲を見回した。変な感じって言われても漠然としすぎていて…。
(学生の頃は何度も足を運んだ場所だけど。喫茶店を継いでからは、経営にも気持ちにも余裕がなかったこともあって、来ていなかったな)
ふとそんなことを思って、過去に何度も見ただろう人で賑わうロゼッタ・ストーンを遠目に眺める。あの展示物の前はいつも人垣ができていて、写真を撮ろうと並ぶ人の光景は昔と変わっていない。
気付けば、リリーはギャラリーのさらに奥へ向かっていた。こういう場所は初めてだと言っていたし、よっぽど展示物に集中しているのか、僕らのことを忘れているようだ。
彼女を追いかけてアッシリアの人の頭をした有翼の獅子像の脇をすり抜ける。
そこでじっと見られているような視線を感じて立ち止まってみたけど、ここでは観光客のアジア人なんてよく見かけるし、誰も僕を気に留めていない。なのにまだ視線を感じる…?
周囲ではなく、上から、な気がしてそろそろと顔を上げると、有翼獅子像の人面顔がこちらを見ていた。「っ、」思わず後ずさった僕の腕をシリルが掴む。彼は怖い顔で像を睨みながら僕を押しやった。
「行くぞ」
引っぱられるまま有翼像から離れ、ようやく僕らと離れていることに気付いて戻ってきたリリーと合流する。
振り返ってみたけれど、像が動いていれば、周囲の人は何事かと声を上げるだろう。でもそんなことは一切なく、人々はいつも通り像の写真を撮ったりしている。そう、動いてなどいないのだ。動くはずのない像が僕を見ていた、なんて気のせい……なんだと思う。
人で溢れたいつも通りの博物館。
過去には何度も通った場所。
アッシリア王のライオン狩りのレリーフを一つ一つ順番に眺めていくリリーは楽しそうで、そこは嬉しいのに、レリーフの中の目という目がこちらを見ている気がして、僕はなんとなくレリーフと距離を取ってしまう。
今日の大英博物館は、学生時代に通った博物館とはどこか違う……。
ここから3章に突入します
先月もちょっと更新サボってたので今月こそはキリキリと!
アリスの小説応援! にポチッとしてもらえると励みになります(ӦvӦ。)
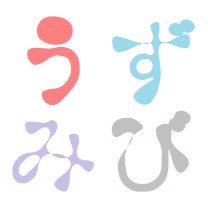






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません