33.逢引
イギリスを代表するファッションブランドの一つといえるトップマンのチェックのスキニーパンツ、寒いからユニクロのヒートテックの上にこれもまたトップマンの無地のシャツを羽織り、同じくトップマンのベストを着用。足元は歩きやすさ重視で、でもカジュアルになりすぎないデザイン入りのスニーカーを履いた。
紅葉は上から下までジロジロと私をのことをチェックすると、『良いでしょう』と頷いた。
そんなわけで、午前10時前にセント・パンクラス駅に着くよう紅葉に部屋を追い出されて、面倒だな~と思いながらも大通り沿いの道を歩いていく私である。
……襟のあるシャツはあまり好きじゃない。首がむず痒いし。
今日の格好はとくに、服に着られてる感じがしてとても落ち着かない。私なんかはユニクロ上下でいいのに。
デート、という単語を使ってきたのはグレースが先だけど、これでスタバの下でいつもの服装でいたらどうしようか…。私だけが気張ってるとかだったら恥ずかしいなぁ。そのときは『紅葉が押し付けてきたんだ』と言ってしまおうか。実際そうなわけだし。
そんなことを考えながらセント・パンクラス駅の煉瓦の建物に到着し、人を避けながらスタバを目指す。
サラサラと揺れる金髪を弄ぶように指に絡め、若干退屈そうな顔で携帯端末の新聞雑誌をめくるのは、チョコレート色の膝丈のドレスを着た彼女だった。フェイクレザー素材のやわらかそうなワンピースで、それだけではさすがに寒いからか、上にもこもことした白いジャケットを羽織っている。足元は丈の短いブーツだ。
「おや、来たね。君にしては早いじゃないか」
こちらに気付いた彼女は電子媒体の新聞を指で払って消すと、若干マシになった顔色にニコリとした笑顔を浮かべた。仕事の付き合い以外では見る機会の少ない、少女らしい笑み。
「そっちこそ、早いね。待たせたかな」
「いいや? 今回は私が言い出しっぺだから」
彼女はこちらまで歩いてくるとジロジロと私のことを見上げた。「いいんじゃないか。そういう君も」それで言うことがこれだから、これは、普段着で来ていたら張り倒されるところだったな。ありがとう紅葉。おかげで命拾いしたよ。

デートと言っても具体的なプランなど何も計画していなかった私とは違い、彼女はしっかりと計画を立てていた。ブーツの足で上機嫌に石畳を蹴りながら「まずはロンドン・アイだ」ビシッとテムズ川のある方を指す。
ロンドン・アイとはロンドンにある巨大な観覧車のことだ。観光場所としては有名どころの一つと言える。
駅からはまぁまぁ遠い。電車でも三十分、タクシーを捕まえても十五分…かな。「移動は?」「タクシーを拾う。ああ、料金は私が持つから心配するな」今日は私が彼女に付き合う日なので、そういうことなら大人しく甘えておくことにする。
捕まえたタクシーに乗り込んで、最短距離の十五分でロンドン・アイに到着した。やはりというべきか、人で混み合っている。
しかし、前もって今日の計画をしていた彼女は用意がよく、チケットはオンラインで購入済み。行列に加わってチケットを取る必要はなかった。
並んで順番を待って十分、巨大なゴンドラに乗り込む。
今日は天気に恵まれ、雲は多いが青空も覗く晴天だ。観覧車での景色も良いものになるだろう。
観覧車がゆっくりと回転していくにつれ、ゴンドラは地上を離れ、人を豆粒のように小さくし、景色はロンドンの遠くまでよく見えるようになっていく。
「どうしてロンドン・アイなんだい」
「デートといえば定番だろう?」
「それはまぁそうかもしれないけど……」
まさか、本気で私とデートがしたいわけではあるまいに。とは言わなかった。彼女が真剣な眼差しで眼下の街並みを見つめていたからだ。
彼女にとっては、ウォッチャーたる自分達がその秩序を裏から支えている街、とも言えるかもしれない。
周囲の人間がロンドンの景色をバッグに写真を撮ったり動画を撮ったりとはしゃいでいる中で、私とグレースは静かだった。
私は今更ロンドンの景色に感動するわけもなく、彼女は、眼下の景色に何かを真剣に考えているようだ。
そのままあまり会話もなく観覧車は地上へと到達し、ゴンドラを降りた、と思ったら細い腕のどこにそんな力があるのかってくらいに腕を引っぱられた。「次だ!」「いてて。ハイハイ、次はどこへ?」「すぐそこの水族館へ!」水族館。魚介がたくさんいるとかいう建物か。
こちらも彼女がオンラインでチケットを手配していたのでスムーズに入場することができた。
魚はもちろん、ペンギン、ワニ、亀、ピラニアなんかもいる、都会のど真ん中にあるために少し規模の小さい水族館は、小さな子供を中心に賑わっていた。
わざと照明を落とし気味にして淡くライトアップされた水槽に注目がいくようにしているその場所の、空気の密度に、私の足は一瞬竦む。
楽しそうに歓声を上げる子供。
水槽には日常では見ることのないカラフルな魚がマイペースに浮遊している。
(思えば、こんな子供くさいところには来たことがなかったな)
いや、どうだったろう。日本にいた頃に行ったことがあるんだろうか。そんな遠い記憶は忘却してしまって憶えていないけど。
毎日休日みたいな私にはすっかり曜日感覚がないけれど、今日は世にいう休日らしい。あっちを見てもこっちを見ても人、人、人。魚より人の方が多いくらい。
地下にあるため館内は全体的に薄暗く、金の髪が鮮やかな彼女のことも見失いそうで、小さな手を取った。驚いた顔の彼女に「デートなんだろう?」なんて気の利いたセリフくらいは言っておく。でもやっぱり恥ずかしいから「はぐれたら困る」と本音も付け足しておく。
ふっと笑みをこぼした彼女はぐいぐいと私の手を引っぱって歩き、ペンギンを眺めたりアカエイに餌をあげたり、カニとイセエビに触れるタッチプールでワンピースの袖をめくると手を突っ込んだりして多いに楽しんだ。
そうしていると、歳相応の少女、というべきか。普段はウォッチャーの顔役なんてやっているから冷静沈着な物言いの少女に見えていたけど、実は全然そうじゃなさそうだ。お嬢様のくせにエビを掴んではしゃいでいる。「見ろ! エビだ!」「そうだね。でも乱暴はダメだよ」タッチするプールであって掴み取りするプールじゃないから。
「そろそろお昼だね。どうする?」
一通り水族館の中を見て回り、グレースがお手洗いに行っている間に考えていたことを、彼女が戻ってきて一番に訊ねる。
時間的にそろそろ考えないと、お店に人が並び始めるだろう。混雑は何事もごめんだ。
エビを掴んだ手をキレイにしてきた彼女はふふんと得意げな顔で携帯端末を振った。「もちろん、予約済みだとも」それでタクシーに押し込まれ、どこへ連れて行かれるのかと思えば、ザ・リッツ・ロンドン。創業百年以上の老舗ホテルであり、王族や著名人に愛されてきた、コーヒー文化が流行ってきたイギリスにおいて未だアフタヌーンティーが絶大な人気を誇る有名店。
いやいや。いやいやいや。「ちょ、待って、ドレスコード…」いくら会計が彼女持ちとはいえ、今日の格好はこんな老舗に入れるようなモノじゃない。聞いてたらスーツの上着くらい持ってきたのに。カジュアルなベストとスニーカーじゃまず無理だ…。
しかし、そこは抜け目のないグレース。ニヤリとした笑みでパチンと指を鳴らした。
どこに控えていたのか、上下黒のスーツとサングラス姿の男が彼女の足元にサッとヒールの靴を置き、僕のベストを脱がせるとサイズがピッタリのスーツの上着、ネクタイ、そして革の靴を用意するし、なんならスーツに似合うチェスターなコートまで持っている。
ここまで用意してでも、彼女はこの老舗、ザ・リッツ・ロンドンに入りたいらしい。
「一度でいいから、ここのアフタヌーンティーが食べてみたくてね。でも一人じゃ寂しいだろう? 付き合ってくれ」
「そうですか…」
淑女らしく手を差し出す彼女に、紳士らしくその手を取る。
百年以上続くホテルであり、未だにドレスコードの伝統を守っていて、それでも人気を博しているザ・リッツ・ロンドンは、扉はドアマンが開けるし、バッグも持ってくれる。
貴族でもなければ著名人でもない私みたいなのには気後れするような豪華な内観は、落ち着いた色の照明と女性が好みそうな色にまとめられていた。アフタヌーンティー、甘いものとくれば、好むのはやはり女性ということなんだろう。
案内された座席に腰を落ち着けたところで、慣れないエスコートに頭のてっぺんからつま先まで気を遣っていたせいかどっと疲れが出てくる。「私には、こういう場所は早いなぁ」紳士淑女。そういう空気のある人ばかりがいる中で、庶民に毛が生えた程度の私は向かない。
グレースはといえば、慣れたものなのか、満足そうな顔で椅子の装飾や天井の細工を眺めていた。「いいなぁ。いい思い出になる」「そうだね…」私は場違いによる心労がすごいけどね。所詮は庶民だよ。
予約していただけあって、アフタヌーンティーはすぐに用意された。歴史のある銀食器に、ティースタンドには下からサンドイッチ、スコーン、ケーキが並んでいる。
紅茶は選べるとのことだったけど、私は味がよくわからないので彼女が言うがままに違う種類のものを頼んだ。
「なぁ、ケイ」
さっそくサンドイッチを取りながら彼女が口を開く。「なんだい」同じようにサンドイッチを選ぶ。段取りとか手順とかよくわからないし、グレースの真似をしよう。
ピアノの演奏が始まり、紳士淑女の空間が静かな会話以外の音で満たされていく。
「君は、生きているか?」
「…どういう意味だい」
「いやね。いつも気になっていたのさ。君は、退屈そうだから」
フォークがサクリと心に刺さったような錯覚を覚える。
私にとって、生きることは、しょせんは暇つぶし。生まれてから死ぬまでの、なるべく楽な道を楽しそうに生きるだけの、そういうモノだった。
サンドイッチを頬張りながら彼女は続ける。行儀とかは考えていないらしい。「君と私は似ている。そういう意味でも、私は君を贔屓していた」せっかくの老舗のサンドイッチを紅茶で喉に流し込んでいる。もうちょっと行儀よく食べなよお嬢様…。
「君は利害を第一に考えて生きて、お金しか信じないし、人のことはぶっちゃけどうでもいい。だろう?」
「まぁね」
「だからさ、私は嬉しかったんだよ。ああ、合理的に生きる人間もいるのだな、ってね」
ウォッチャーのリーダー、その顔たるグレースはスコーンに手をつけた。たっぷりのクリームをつけてあーんと大口を開けている。…だから、行儀。お嬢様。
「だけど、君は、最初からそう生きたかったわけじゃない」
サクリと心にフォークが刺さって、サンドイッチの味もよくわからず飲み下し、グレースの真似をしてスコーンに伸ばしかけた手が止まる。「君は天才になんて産まれたくなかった。そのせいでイギリスに売られたし、そのせいで人が信じられなくなった」「…………それが、何」今日はずいぶんと個人的な話をしてくる。
今日は君に付き合うと決めたけど、そんなにズカズカ入ってこられるのは得意じゃない。ポーカーフェイスは得意な方だと思ってるけど限度がある。
スコーンをペロリと平らげた彼女は、一番上のケーキを選び始めた。どれにしようか迷っているようで指が彷徨っている。
「君が合理主義なのはそうするしかなかったからで、お金しか信じないのは、それしか信じられるものがなかったから。あのAIだって、機械は自分を裏切らないからそばに置いているんだろ」
「だから、何。なんでそんな話をする」
「うん。そういう君は『生きている』って言えるのかなって。人間の生きるって、もっと違う形なんじゃないかと私は思うから」
青い瞳がこちらを見据えている。
グレースが金髪のこともあって、竜たる彼女に見つめられて死にかけたことを思い出し、それをノアが庇ってくれたことも思い出す。
紅茶の味は、良し悪しは、よくわからない。この曖昧さがいいのかもしれないけど、私は手軽でハッキリとしているコーヒーの方が好きだ。苦いとか、苦くないとか、ちょっと酸っぱいとか、一口飲めば舌が馬鹿な私にも少しはわかるし。
ああ、ノアの淹れたコーヒーが飲みたいな。
「義務的に生きて、義務的に死ぬ。それは人生と呼べるものかい?
私は、君に自分の人生を生きてほしいと願っているよ」
油断したらまた更新が途絶えてました。。
アリスの小説応援! にポチッとしてもらえると励みになります(ӦvӦ。)
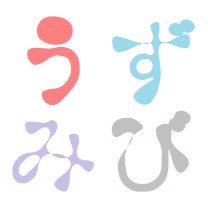






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません