32.帰宅
コンパートメントの一室に陣取ったぼくは、ロンドン、セント・パンクラス駅行きの列車に乗っていた。
向かいには紅葉がいて、荷物を詰め込んだトランクを座席の上の棚へと上げたところだ。
『まもなく発車です』
「うん」
『よろしいのですか?』
「…うん」
ぼくは窓枠に頬杖をついて、ぼんやり、見送る者のいない無人駅を見ている。
仕事は終わった。喫茶店ドラゴンでやるべきことは終わったのだ。だからこの場所を去る。ロンドンに借りているアパートに戻る。ウォッチャーの彼女に報告をする。お金をもらう。それでしばらくまた暮らしていける。何も問題はないはずだ。
ぼんやり窓の向こうを眺めていると、列車がガタゴトと揺れた。動き出したのだ。
そんなときになって、無人駅に駆け込んできたのは、ノアだった。「あ…」思わず身を乗り出す。列車は容赦なく駅を離れ始めている。
窓を上へとスライドさせて首を外へ突き出すと、ぼくに気付いたノアが手を振った。
「ケイ! またっ!」
また。
また会おう、って? 仕事でやってきただけのこのぼくに?
突き放さなくては、と思う。お互いのために『もう二度と会わないよ、サヨウナラ』と言わなくてはと思う。
だけど口からは細い息がこぼれただけで全然声にはならなくて、彼の姿も田舎の駅もあっという間に小さくなってしまい、ぼくは紅葉に首根っこを掴まれる形で列車内に戻された。『危険です』ピシャン、と窓を閉じた彼女に「ごめん」と返して座席の背もたれに深く背中を預ける。
(また。また……かぁ)

長く列車に揺られて降り立ったセント・パンクラス駅はそれなりに久しぶりだったけれど、相変わらず人で混み合っていた。そこかしこでクルクルと踊るように回転する立体広告が鬱陶しい。
あの田舎町にはこういったものが一つもなかった。せいぜいスーパーやレストランで見かけたくらいで、情報で溢れている都会の駅という空間で束の間立ち止まり、こめかみをもみ解す。
ここがぼくの居場所だ。思い出せ。
紅葉にトランクを任せてトイレに行き、そこでぼく、滝沢蛍は消えて、代わりに天才魔術師Kが現れる。
人と広告でうるさい駅を早々に離れ、ロンドンの人混みの中を抜けてウォッチャーご用達の赤い電話ボックスまで行った私は、紅葉を外に待たせ、電源を切っていた端末を再起動させる。
何回やっても面倒な手順の手続きのアレやコレやをすませ、ようやく繋がったと思えば、ウォッチャーの顔たる金髪碧眼の少女は酷い顔色の立体映像として現れた。「ええ…」思わずちょっと引く。なんだその死人のような顔は。今にも倒れそうじゃないか。
『君か。久しいね』
「そうだね。っていうか何その顔…すごいよ? 寝てないの?」
『まぁ。忙しくてね。ウォッチャーは常に仕事が山積みなのさ』
「それはわかるけどね。君に倒れられても困るよ。ウチのお得意サマなんだから」
彼女は苦笑して私の小言を流すと、コホンと一つ咳払いをした。『それで? 成果はあったかい』「まぁ…ね」ちらり、と辺りを窺う。紅葉が外で見張っているし、ここはウォッチャーが情報操作をしている。誰に漏れるわけでもないのに、私の頭にあるのは、内緒ですよと人差し指を立てたノアのことだった。
内緒にしてくれ、と言われた。
シリルは私を信用していないままだが、ノアは違う。私のことを、滝沢蛍のことを信じて話をしてくれた。
唇を噛む。
常連客に成りすまし、仕事を理由に騙したのに、彼は私を怒らなかったし、私に落胆もしなかった。
私は彼を裏切りたくない。
『どうした、K』
「…成果、なんだけどね。自衛のため、詳細を省かせてもらっても?」
『構わないよ』
「アーヴァイン・ブラッドは確かに死んだ。彼は今後二度とウォッチャーを困らせることはない」
おそらく言葉の続きを待っていたんだろう彼女は、こちらがそれ以上喋らないとわかると驚いたように目を大きくして口をぽかんと開ける。『それだけかい? そう断言する根拠や証拠は?』「…………」『K。君とはそれなりに長い付き合いだ。君の言葉を信用したい気持ちはあるが…』頭を振った彼女は苦い顔をしている。
ああ、わかっているとも。これじゃ前回から調査に進展があったとは言い難い。『ブラッド卿は死んでいる』『リリー・ブラッドは生きている』…これ以上の情報を、私は彼女に渡せない。
黙っていると、彼女は大きく息を吐いた。『その内容だと、これ以上の報酬は支払えないが、いいかな』「ああ」『そうか。では』通話を切ろうとした彼女が、ふっと思いついたように伸ばした手を引っ込めた。
『なぁ、ケイ』
彼女は私のことを天才魔術師Kとして接するが、時折、ケイ、と滝沢蛍のことを呼ぶ。そういうときは私のことを天才魔術師Kとして求めているのではなく、一個人として話している。
彼女が私のことを一個人として話すのなら、こちらもそうしよう。「なんだい、グレース」普段はウォッチャーの顔として、グレース・クラークとして立つ少女は、今はただのグレースとして指を振っている。『三日後、久しぶりに丸一日休暇をもらえるんだ』まるでブラック企業に勤めているかのような発言をした彼女の顔色はやはり悪いままだが、表情はやわらかい。休暇が嬉しいのだろう。私は毎日休みみたいなものだからよくわからないけど。
『君、三日後に私に時間をくれないか。それで今回の件はお互いチャラにしようじゃないか』
「は?」
思わず顰め面になった私に彼女は得意げな顔で指を立てる。『美少女とのデートだぞ。嬉しいだろう』「ええ…?」彼女のことをキレイじゃないとは言わないが、別にタイプというわけでもない。嬉しいかと訊かれると微妙なところだ。
嬉しいかは実に微妙なところだけれど、スッキリしない終わり方になった今回の依頼を、これで終わらせてくれるというのだ。グレースの申し出に付き合う以外の道があるだろうか。
仕方がないので了承した私に、彼女は三日後の午前10時にセント・パンクラス駅のスタバ前で落ち合う約束を取り付け、通話を終える。
そんなに神妙な顔をしていたのか、電話ボックスから出た私を見て紅葉が『いかがなさいましたか』と問うてくる。「いや……うん…」なぜかグレースとデートしなくてはならなくなった。そんな話をしたら紅葉はどういう顔をするんだろうか。
アパートに戻った私は、誰に見せるわけでもないが、列車の中で書き起こした文章を改めて読み返していた。
アーヴァイン・ブラッドが喫茶店ドラゴンに身を寄せる竜を狙っていたこと。シリルやリリーはその手先としてやってきたこと。けれどノアの人格と竜の助けによって二人はブラッド卿から離れ、対峙し、今はノアのそばで弱った竜を守っていること…。
『おじい様の行方はわかりません。彼女も、そう言っていました』
リリー・ブラッドは祖父についてそう供述している。
最後にアーヴァイン・ブラッドと対峙した金の竜…人の姿のときは金髪の女性になる彼女は、私と口を利くことはなかったが、リリーの言葉を否定もしなかった。
出会ったばかりで信用がないのだから当然なのだけれど、私の前で彼女が竜に戻ることはなかった。
が、シリルの目を魔眼と警戒して施していった術を無効化して全身を縛ったあの蒼い瞳。見る、という行為だけで他者を縛り、息を止めるところまで行ったあの瞳は、魔眼以上のものだ。それが竜のものだというのなら納得もできる。
竜が。ドラゴンが。生きている。
長いこと生きた固体は確認されていなかった、もはや伝説上の生物だとされていたものが……。
『オレとリリーに竜をどうこうしようなんて考えはない。オレらはノアの意志に従うだけだ』
シリル・キーツ。リリー・ブラッド。二人は魔術師の一端であるが、竜に興味はないという。ただ、竜を匿うノアに従うだけだ、と。
そのノアにも、竜をどうしようとか、こうしようとか、そんな考えはなく。彼はただ『彼女が元気になってくれれば』と、心配そうな顔で人ならざるモノを見つめるのみだ。
(竜、ドラゴン、で思い出したことがある)
アーヴァイン・ブラッドが天才と呼ばれていた最後の頃の話だ。
彼は『森でドラゴンに会った』と吹聴していた時期があったそうだ。
生きたドラゴンの存在が確認されたのははるか昔。かの幻獣はすでに絶滅したか、人間から隠れるため遠い場所へ行ってしまっただろうというのが通説であり、『ドラゴンに会った』と言う天才の声に、さすがの魔術師たちも失笑したのだとかなんとか。
彼の言動はその辺りを境におかしくなっている。
(つまり……天才は、己を超える才能に溢れた生物を見て、おかしくなったのか…?)
それとももっと深い縁でもあったのか。
とにかく、ブラッド卿がノアのもとにいたドラゴンを執拗に狙ったのにはそういった理由もあったということだ。
ブラッド卿は死んだ。遺体を確認したわけではないが、竜という生物が嘘を吐く理由はない。嘘と偽りは人間の本分だ。竜が死んだと言うのならそれが真実だ。
情報保全のためネット接続できない記録用の端末の電源を切り、枕の下にしまう。
そのままベッドに寝転んでしばらく。ぼんやりとコーヒーが飲みたいなと白いカップに注がれた黒い液体を思い出していると、トランクの中身を片付け終えた紅葉がやってきた。
『今後はいかがなさいますか』
「んー……。とりあえず三日後。予定がある。ウォッチャーの彼女とデートなんだ」
そうぼやいたら紅葉がカッと目を見開いた。部屋で生活感のあるものの一つである壁掛けカレンダーに高速でハートマークをつけたかと思えば私の服が入っているクローゼットを開け放ち、『デートのための衣服がありません』と、これまたサラッと言ってくれる。「普段着でいいだろう?」『反対です』「えー…」しまったなぁ。デートなんて言うんじゃなかった。
しかも、ここで嫌なことを思い出した。シリルに服をダサいって言われたことだ。「…はぁ。くそ」仕方なく体を起こし、一度脱いだコートをもう一度着る。
「じゃあ、紅葉が見繕ってよ。自分じゃよくわからないし」
『はい』
しっかりと頷いてついてくる気満々の紅葉に吐息し、今帰ってきたところなのに、私はもう一度、今度は服を買うために外出するのだった。
小説強化月間を終えたらまた気が抜けて一ヶ月更新しなかったアリスです
あかんて。せめて毎月更新を心掛けたい…!
ウォッチャーの彼女がようやくちゃんと紹介できた気がする~
2章はもうちょっとでおしまいなのでサクサクいきたいなぁ
アリスの小説応援! にポチッとしてもらえると励みになります(ӦvӦ。)
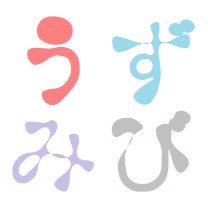






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません