20.黒い一夜
牢屋。
そう称するのが適切だろう、簡素な台に布が敷かれただけの寝台に腰かけ続けて、どのくらいの時間がたったのか。
壁には正視するのに勇気がいるような酷い傷が多い。
爪が剥がれるまで引っかき続けたのではないか、と思う鉄扉の引っかき傷。それが視界に入る度に自分の爪をつい確認してしまう。僕のは、ちゃんとある。
天井から鎖でぶら下がっている、拷問に使われたんじゃないか、と思える鈍い色の鉄の枷は、ときどき風もないのに揺れている。
床には血痕のような黒ずんだ汚れがこびりついたままになっている。
たまにクスクスと笑うような声も聞こえる。それはリリーの声じゃなくて、もっと直接、頭に響くような笑い声。
思考をやめてしまうと、この空間にいる何かに取り込まれてしまう気がして、ここで目を覚ましてからずっと、僕は何かを考え続けている。
(シリルはどうしてるだろうか。ドラゴンの彼女も)
僕にはなんの力もなくて、彼らの足を引っぱってしまっている。
狙われているのは僕じゃなく、ドラゴンの彼女だ。僕が捕まったのは、たぶん、人質。僕の命が惜しいなら…というやつ。
まるで映画のような展開だな、なんて思ってみたところで慰めにもなりはしない。
僕はシリルと違ってなんの力も知識もなくて、無力だから、人質にはもってこいの存在だったろう。
こんなことになるのなら、シリルにも、彼女にも、もっと色々聞いておくべきだったかもしれない。魔術とか、魔力とか、そういうモノのことを。知ったところで自衛ができたのかは怪しいけど、無知であるよりはマシだったかも…。
ぼんやりと考え事をしていると、くん、とスウェットを引っぱられた。
目を向けても誰もいないのに、見えない何かがそこにはいて、僕の服を引っぱって遊んでいる。
知らない世界の中に一人放り込まれて、正直かなり厳しい。知らないことが洪水のように容赦なく僕を襲い、もみくちゃにして、牢屋で孤立した心は疲れ果てている。背中は冷や汗で冷たいし、冷静ぶって考え事を続けているけど、今すぐ喫茶店二階の自室のベッドで眠りたいくらいには疲れている。
それでも、逃げたくはない。
見てない、知らない、って背を向けたくはない。
この冷たい世界は確かに在って、そこにはシリルもリリーもドラゴンの彼女もいるのだ。僕はその世界に蓋をしたくはない。
みんな家族だ。
そのくらい、大切だ。
家族のことを知りたい。みんなが置かれている状況を理解したい。
僕の根っこは単純で、かけがえのない人のために、全力で走る。取り組む。手を伸ばす。それだけなんだ。

ガチン、と鉄扉の扉から音がして、寝台に横になっていた僕は薄く目を開けた。…いつの間にか意識が落ちていた。意識を落とさないようにと考え事を続けていたつもりだったけど、気絶、していたんだろうか。緊張しすぎて、意識の糸が切れたのかな。
ギギギと不吉な音を立てて開いた鉄扉の向こうには、杖をついた小柄な老人と、その後ろに控えるようにして無表情のリリーが立っている。
見知った顔を見たためか、僕は少し安堵していた。そのせいか、この部屋にあれだけ満ちていた何かの気配がもうなくなっているようにさえ思う。
「ほう。案外と図太いようだな」
僕がこの牢屋で寝ていた事実にそう感想をこぼした老人は、カン、と杖で石の床を叩いた。
リリーが無表情のまま歩み出てきて、手錠をつけている僕に「立ってください」と言う。その声にも感情はない。
リリーに背中を押されるようにして牢屋の外に出て、背中を押されるまま石の階段を上がる。
不可抗力で事件に巻き込まれた場合、犯人の要求に逆らわないことは鉄則だ。
とくに今回は、僕はただの人間で、でも、相手は魔術とかそういうのを使える人たち。僕には一ミリの勝算もない。抵抗するのは賢い選択じゃない。
石段を上がりきっても暗い視界で、リリーに背中を押されるままに歩いて、何かに躓いてしまった。あ、と思ったときには視界が傾いでいる。転ぶ。
けど、予想した衝撃はこなかった。リリーが僕に腕を回して踏み止まったからだ。「ありがとう…」ついいつものリリーに対する口調でお礼と笑顔を浮かべてしまって、無表情のリリーに、僕の笑顔は行き場がなくなる。
連れて行かれたのは、灯りのない暗い屋敷の外。
「……?」
薄暗く色のない屋敷の外は、星一つない、真っ暗な空をしていた。
真っ暗。いや、真っ黒、と言ってもいい。空じゃなくて夜の海を見ているみたいだ。海が頭上にあるなんておかしな話だけど……。
「ドール」
「はい」
「ソレを檻に入れておきなさい」
老人にドールと呼ばれたリリーは、ソレ、と顎でしゃくって示された僕を無表情に見つめた。
真っ赤なドレスを着ているリリーのケープの部分がひとりでに外れ、地面に落ちたかと思うと、赤い血の塊へと溶解した。それが滑るように僕の足元にやってきて真っ赤な鉄格子を生やし、檻を形成する。
……おそるおそる、手を伸ばして、赤い鉄格子に指先で触れてみた。
それは確かに血の色をしていて、あたたかいのに、本物の鉄のように硬かった。素手じゃどうしようもなさそうだ。
無力な僕は、金のドラゴンたる彼女を誘い出すための人質。
僕は祖父の喫茶店を継いだだけの、アジア人顔をしたイギリス人。価値のある人間かそうでないかと訊かれたら、間違いなく無価値な人間だ。
そんな価値のない人間なのに……僕を助けるために、真っ暗な空をぶち破って、シリルが飛び込んでくる。左目が光ってる。彼の後ろには本物の空と、金色の彼女がいる。やっぱりみんな来てしまった……。
「ノアっ!」
真っ黒な翼を生やしてまっすぐ僕のもとに飛んだシリルに、赤い翼を生やしたリリーがぶつかっていく。「リリーっ、シリルも、やめてくれッ!」僕が声を荒げたところで二人は止まらない。止まれる理由がないから。シリルは僕を助けるために、リリーはそうはさせないために。二人の目的は一致しない。だから戦うしかない。やめろと声を上げながら、そうできるはずがないと、僕もわかっている…。
ナイフを手に空中戦を繰り広げる二人はあの夜の再現のようで、胸が痛い。二人にあんなことしてほしくないのに。
金色の彼女は、今は白いワンピースに茶色のブーツを履いて、クリーム色のコートを着ていた。
この異様な空間の中で、彼女だけがいつも通りだ。リリーとシリル、そして僕のことを凪いだ瞳で見つめて、それから、目の前の老人に顔を向ける。
皺だらけの顔をした老人は、金色の彼女を前にして目を見開いている。その周囲に蠢く影のような昏い何かは、僕の知らない世界の産物たち。
「五十年になる。実に、実に長かったぞ。ようやくその力をモノにできる……」
真っ黒な、作られた空が、シリルがぶち破った穴を修復して落ちてくる。重力に引かれるように、その天井を低くしている。
僕は、何もできない。わかっている。生きる世界が違う。
でも。それでも。何か。できないだろうか? シリルのために。リリーのために。ドラゴンの彼女のために。できることは……。
おいしそうだなぁ
ふと響いた声に顔を上げる。
そばには誰もいない。リリーが血色のナイフを飛ばし、シリルが月光色のナイフでそれを弾いて、金の彼女は静かに立っている。すべての元凶だろう老人は彼女のことしか見ていない。この小さな世界のほとんどは彼女へと意識を向けている。
(じゃあ、今のは、誰の声だ?)
なんだか、ひどく、喉が渇いている。
甘いキャンディだ。なぁ
また。声がする。甘い、キャンディ…? 一体なんのことを言ってるんだ。
クスリと誰かが耳元で笑った。思わずそちらの耳を手で押さえる。当然、誰にも当たらないし、ぶつからない。この檻の中には僕しかいない。ならこれは誰の声だ?
羨望が憎悪に変わったのさ。だからアレは過去に煌めいた、かつては眩しかったモノ。それが変貌した
僕の視界の外から黒い指が出てきて老人を指した。目を向けてもやっぱり誰もいない。
だけど声を発するナニカは僕の近くにいて、耳元で、そういうものはうまいんだよ、と笑う。
背筋が冷たい。冷や汗が止まらない。
僕にはどうしようもないモノに語りかけられているのは、わかる。わかるのはそれだけだ。ソレが何を言いたいのか、何がしたいのかはわからない。
「きみは、なんだ」
問うた僕に、声はただ笑うだけ。
20話め!
昨日間違って公開ボタンを押していたようで、慌てて手直ししました💦
ノアはもともと人間関係が希薄(本人は友達とか作りたいけどアジア人顔のせいで人が避けていく)で、友人も得難い人生を歩んできたので、一度得た大切な人は大事にしようという意識が強いです
そのためならなんでもしようという覚悟もあったりします
アリスの小説応援! にポチッとしてもらえると励みになります❤(ӦvӦ。)
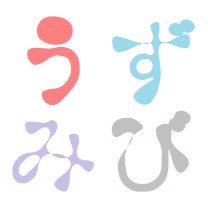






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません