1.喫茶店『ドラゴン』には妖精がやってくる
風雨に晒され、月日の経過で朽ちていくばかりの看板。年季の入った丸テーブルとチェア。
イマドキ骨董品扱いのブラウン管のテレビの調子は今日も悪く、ザラザラとノイズを混ぜた音を吐き出しながら、なんとかサッカー中継を流している。
田舎町の寂れた喫茶店『ドラゴン』は、今日も閑古鳥が鳴いている。

観光名所というわけでもなく、避暑地というわけでもなく、自然が豊富というわけでもない。そんな無名の町にただ昔から存在している喫茶店には今日もお客さんらしい人は来ない。
店主、である僕は、ひととおり、人を呼び込む努力はしてみた。
手書きのビラを家々のポストに入れたり、メインストリートで配ってみたり、店の見栄えをよくしようとガーデニングを始めてみたり、この町にもっと馴染もうと集会やボランティアにも参加した。
結局、ガーデニング以外はうまくいかなかった。
ビラについた割引券を使いに何人かは店に来てくれたけど、それっきり。二度目はなかった。
『シュート! 先制点です!』
ザラザラとノイズ混じりのテレビの声。
レポーターの叫ぶような声を聞くともなく耳に入れながら、僕は無言で、手元のカップを磨いている。
この店をおじいちゃんから継いで、一年になる。
おじいちゃんが切り盛りしていた頃は、この店は町で馴染みの喫茶店として親しまれていた、らしい。
けれど、僕がカウンターに立つようになってからは『親しまれている』なんて感じることはなく、むしろ『避けられている』と感じることの方が多い。
それもこれも。僕が東洋人の顔立ちをしているから、だろう。
母の血を濃く継いだらしく、生まれも育ちもイギリスなのだけど、限りなく日本人に近い顔立ちをしている僕は、街に出れば毎度観光客と間違ってセールスの声をかけられる。
そんな日本人風の僕は、この町に住む人には奇異に映るらしい。
日本なんて東の島国。それも最近、ついに先進諸国の中から外された国だ。そんな小さな国のことは知らなくて当然だと思う。
僕も、顔こそ日本人だけど、日本へは母の実家へ遊びに行くときに訪れたくらいで、日本のことはよく知らない。そんな『よく知らない国の若者』が馴染みであった喫茶店を継いだ…。この町の人にとっては眉を顰める出来事にもなるだろう。
僕がこの町に馴染むにはそれなりに時間がかかる。それは最初からわかっていたことだし、覚悟していたことだった。
それでも。
ただ茫漠と過ぎていく日々。何にも関われず、何とも交わらない時間が長く、長く続くと、僕は何をしているんだろう、なんて気の迷いも覚える。
(おじいちゃんにも言われたじゃないか。お前が町に受け入れられるまで、長くかかるだろう、って。お前のじーちゃんの儂でもそうだったんだから、って)
最後の方はベッドで寝たきり状態になっていた父方の祖父のことが、僕は結構好きだった。
最初は日本人の顔をした僕を邪険に扱っていたおじいちゃんだったけど、孫はやっぱりかわいかったんだろう。仏頂面でも僕を抱き上げたし、散歩に連れて行ったし、公園でボール遊びに付き合ってくれた。
最初におじいちゃんが笑ったのは、僕が学校で家族の似顔絵を描いたときだったっけ。
あの日を境に僕とおじいちゃんは仲良くなった。
おじいちゃんが淹れるコーヒーが好きだった僕は、自然と、おじいちゃんのお店を継ごうと思った。
父とはそのことで対立した。母が間に入ってくれてなんとか収まったけど、父は今でも僕に「堅実な道を行け」と言ってくる。
父が正しいのだろう。これは茨の道だ。そう覚悟しながら一人で喫茶店ドラゴンの古い扉を押し開けたのが一年前。
以来、孤独に日々を過ごしている僕が縋れるものは、少ない思い出達だけだ。
堅実な道を行け、という父の言葉が、日々重みを増して僕にのしかかってくる。
…無駄な抵抗だと思うけど、せめてこの黒髪を染めてみようか。明るめの茶色とかに。黒はとにかく浮くし。今更、かもしれないけど。
「コーヒーをください。ホットで」
ノイズ混じりのブラウン管テレビのサッカー中継が流れる店内で、ポン、と軽く落ちた声。
カップに落としていた視線を上げると、いつの間にか店の入口に人が立っていた。
無表情でカップを磨いていた僕は軽い驚きとともになんとか笑顔を作って「いらっしゃいませ」と久しぶりのお客さんに声をかける。
白いワンピースに、金糸のような金色の髪がサラサラと揺れるのが印象的な女性だった。
この町で見かけたらきっと忘れない。観光だろうか。こんな何もない田舎町に。
親戚とかを訪ねてきたのかもしれない、と考えつつ、毎日淹れる練習は欠かさないコーヒーを手順通りに淹れ、砂糖とミルク、おまけのクッキーを二枚つけて女性のいるテーブルに置く。
女性はコーヒーをじっと見つめてからカップを両手で持ち上げた。
いまだに慣れないのだけど、僕は、自分が淹れたコーヒーを提供するとき、緊張する。
万人が「おいしい」と笑う正解という味は存在しない。そうわかっていても、僕のコーヒーは気に入られるだろうか、と無意識に考えて、心が身構えている。
女性はコーヒーを口にした。一口。二口。それからおまけのクッキーを細い指先でつまんで持ち上げる。
「不思議ですね。同じ味がします。あのおじいさんと同じ味」
「祖父をご存知でしたか」
「よく知っています。常連なので」
「それは、失礼しました。祖父は…その」
祖父は、家族に見守られながら逝った。そのことをどう伝えようかと言葉に迷っていると、女性は悲しそうに目を伏せて「わかっています」とこぼし、クッキーをかじった。
『いいかい、ノア』
そんなはずはないのに、耳元で、おじいちゃんが囁く声がする。
『お前が店を継ぐのは、お前の自由だ。だけどこれだけは憶えておくんだ。
あの店には、妖精がやってくる。
決して、失礼のないように』
それは、おじいちゃんがうわ言のように僕に繰り返していた言葉。
その意味が最後までわからないまま、おじいちゃんは逝ってしまった。
(妖精)
店の常連だという相手はきれいな女の人で、おじいちゃんが親愛の意味のようなものを込めて彼女のことを『妖精』とたとえたなら、それはそれで納得はできる。
おじいちゃんに妖精とたとえられた女性がカップを手にしたままこちらを見つめていることに気付いて、僕はなんとか笑顔を作る。
「どうかされましたか?」
「わたしのことを、おじいさんから聞いていますか」
「…ええと」
さっき思い出した言葉は、そういうことになるのだろうか。
それにしたってなんてタイミングだろう。ついさっき思い出したことを訊かれるなんて。
僕は迷った末に、おじいちゃんの言葉を伝えることにした。
「この店には、妖精がやってくる。決して失礼のないように…と言われました」
女性は無表情に一つ頷くと、「おじいさんが信頼を置いたのなら、わたしもあなたに信頼を置きましょう」と言って、カップをテーブルに戻した。
そして、彼女は竜になった。
それはとても自然に。射し込む陽光のあたたかさに羽織っていた上着を一枚脱ぐような、そんな自然さで、彼女は人から竜になった。
僕は磨いていたカップを危うく床に落としそうになり、慌ててキャッチする。それから恐る恐る、金色で、キラキラと輝く四対のガラスのような羽根を羽ばたかせている竜へと視線を向ける。
竜は空のように澄んだ蒼い瞳でこちらを見ている。
そして、言う。
『力を、貸していただきたいのです』
これは、おじいちゃんが遺した喫茶店『ドラゴン』で起こる、不思議な物語だ。
文章が趣味なのでなんとなく書き始めました
気が向いたらまた書きに来ます!
応援! にポチッとしてもらえると励みになります❤(ӦvӦ。)
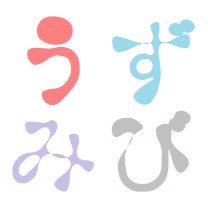






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません