【完結】アニリン⑦
このお話は、DDONのフィンダム大陸に出てくる敵『グリーンガーディアン』と少女を主体にしたお話です!
グリーンガーディアンはこんな魔物です↓

今回で7話めなので、「まだ前の話読んでない!」という方は以下からどうぞ↓
ここまでお付き合いありがとうございました!
少女アニリンとグリーンガーディアンの物語はこれにて終幕です!
一人と一匹はどこへ向かうのか…。どうぞ!
去り際のアニリン
なるべく誰も巻き込まぬように。
なるべく誰にも見つからぬように。
なるべく、静かに、過ごせるように。
そう考えたオレが向かった先は、キンガルだった。
そこかしこに毒が蔓延しているその地域に住む生者は少ない。亡者のようなモノが巣食っているその地なら、生者に気遣いをせずにすむ。そう考えたのだ。
静かに過ごせればいい、とは思うが、あまり期待はしていない。だが、一応努力はしてみようと、静かな場所を探した。
廃村。遺跡。神殿。地下道。川岸。そのすべてに何かしらの生物だったモノが巣食っており、ときには縄張りを争っていたりもした。
どこも先客で溢れている。腰を落ち着ける場所はなかなか見つからない。
肉体を失ってなお自分をハーピーだと思い込み飛び続けている影の鳥を追い払い、片目の視界で森に入る。腐った森はひどいニオイがしたが、影の鳥につつかれ続けるよりはいい。
ガサガサと茂みを鳴らしながら歩いて、足元に躓いた。何かと思えば、地面に半分同化するような形で、人の、骸が、転がっていた。半分が食われ、半分が放置され腐っているという有様に思わず眉間に皺が寄る。
踏み出した足を引いて、ルートを変える。
こういうモノが放置されている場所は避けた方がいい。力を誇示したがる面倒なヤツがいる可能性が高い。
その後もキンガルのあちこちを歩き回ったが、ここだ、と思える場所は見つからなかった。
(先客がいなさそうな場所など、もうあそこくらいか…)
気は進まなかったが、道を引き返し、シェドレアン大神殿、と呼ばれていたらしいひときわ立派な神殿に向かった。もちろん、魔物の巣窟となっている神殿内には入らない。
神殿前の脇道から、川のギリギリを行き、濁った泥のような色の水に、覚悟を決めて飛び込んだ。ドボン、と飛沫が上がる。
キンガルの水は、まるで本当に泥のように重く、体にまとわりつく。
少し泳いだ先にある、いくつかある小さな島のどこかに居を構えられればいい。出入りのたびに泳がなくてはならず危険は伴うが、キンガルの地は先客で溢れかえっている。可能性はあの離島くらいしかない。
泥よりもマズい水を何度か飲むことにはなったが、泳がねばたどり着けない小さな島には先客の姿はなかった。浜から木の虚まで丁寧に調べたが、誰の姿もない。よかった。ようやく居住となる場所を見つけた。
寝床になりそうな虚も見つけ、ここでいいだろう、と腰を落ち着け、ふと顔を上げて……虚しさを覚えた。
見えるのは泥のように濁った水と、今にも雨が降り出しそうな重い色の雲に、枯れた草木と廃墟。
聞こえるものは鳥のさえずりではなく、魔物の咆哮や威嚇の声。
…アニリン。
彼女から離れてこれで一週間だ。彼女はどうしているだろう。
(………忘れなくては。アニリンも、オレのことなど、忘れればいい)
そうとも。オレはアニリンのことなど忘れる。だから、薄情なヤツだと罵って捨ててくれればそれでいい。片角どころか片目まで失ったオレのことなど忘れてしまってくれ。どうか。どうか……。
「おねえちゃん?」
夜も更け、けれど、朝にもまだ遠い、という時間にそっと起き出したのに、あの子が目を覚ましてしまった。わたしを受け入れてくれた心優しい一家の一人娘、ジュネスだ。今年で八歳になる。
左腕のないわたしを怖がるどころか、手助けしてくれた、よくできた女の子。
できれば、ジュネスにだけは起きてほしくなかった。…もう、遅いけど。
わたしはなるべく上手にジュネスに笑いかけた。眠いのだろう、目をこすってわたしを見ている彼女に、左腕を隠しながら、上手な言い訳を考える。「ちょっと、トイレだよ」「よるは、あぶないよ」「うん。ガマンしてたんだけど、限界なんだ」キイ、と静かに扉を開ける。「すぐ戻るね」私の下手な言い訳をあの子はどう受け止めただろうか。最後まで、あの子は眠い目をこすりながら、わたしのことを見ていた。
パタン、と静かに扉をしめて、つかの間、祈った。
どうか、この優しい一家に、わたしの病がうつっていませんように。
どうか、この優しいひとたちに、わたしの分も、幸福が、訪れますように。
ジュネスに教えてもらった文字を刻んだ木板をドアの横にそっと立てかける。
直接、お世話になったお礼を言えないわたしを、どうか罵って。恩知らず、と恨んでくれればいい。…きっとそんなことはしない人たちなのだろうけど。ただ、いなくなったわたしに残念そうな、心配そうな、そんな顔をするのだろうけど。
(今まで、お世話になりました。優しくしてくれて、ありがとうございました)
わたしはもうここにはいられない。
そっと左腕に視線を落とす。きつく包帯を巻いて誤魔化していた二の腕から、緑色の、棘のようなものが突き出していた。…もう包帯で隠すのも限界だ。この病が心優しいこの一家にうつるのも忍びない。だから、わたしは、行かないと。
片腕しかなくなったわたしに弓は不要になったから、かわりに、ナイフをいただいた。
弓と交換ということで、ごめんなさい。いただきます。
片腕での山登りは苦労したけれど、わたしはまず、あの子を探した。グリーンガーディアンのあの子だ。
最近はあの子の視線も気配も感じなくて、感じられなくて、とにかく心配だった。
わたしの記憶が正しければ、この樹木の辺りで生活していたはず…。そう思って少し開けたその場所を調べてみたけれど、あの子の痕跡はない。「いないの?」そっと声をかけても、そこには静寂しかなかった。
あの子は移動したのだ。わたしをあの一家に預けて。一人で。
どうしてそんなことをしたのか、可能性は二つある。
一つめは、わたしが毒に侵されたから。だから捨てた。自分の安全を考えて。
でも、それはたぶんありえない。
そんなことができるなら、あの日あのとき、ピクシーに襲われるところだったわたしを助けて、その世話を焼いたりしなかったはずだから。
だから、必然、二つめの可能性が、あの子がわたしから離れた理由になる。
わたしが発症したのは、毒に侵されたグリーンガーディアンにやられたから。
なら……片目を抉られ、毒を撒き散らすあのグリーンガーディアンと体をぶつけあったあの子は、わたしよりも毒をもらっていたんじゃないだろうか?
だからわたしから離れた。わたしの毒の侵攻を早めないためにも。
(バカだなぁ)
食べられそうな木の実を摘んでポケットに入れて、気合いを入れるために、パン、と片手で自分の頬を叩いた。
さあ、ここから長旅になる。装備はナイフだけ。食べ物は現地調達。
気合いを入れるのよ、わたし。一人旅は初めてなのだから。
それにしても、バカだなぁ、あの子は。
わたしも、きみも、同じ状態になったというのなら。どうしてそこで離れることを選ぶだろう。
たとえ、それで病が早くにわたしたちを支配したとしても。いずれ支配されるのなら、どうせ終わりが来るのなら。一時でも穏やかな時間が過ごせるのがいいに決まってるのに。
わたしにとっての穏やかな時間は、優しい一家と一緒にいることじゃない。毎日竜に祈りを捧げて食事をいただくことじゃない。
名前も知らない、グリーンガーディアン。長く一緒に生きてきた、あなたと一緒にいることなんだよ。
「名前を、あげても、いいのかな。いいかげん、名前を、呼びたいな…」
アニリン、と、あなたがわたしを呼んでくれたように。何度だって、わたしを呼んでくれたように。わたしも、きみを、呼んでみたいな。
砂利道を踏みしめてエランの山道を行く。名前も知らないあの子のことを考えながら。
あの子なら、わたしの足でも近いと感じるエランやファーラナには留まらないだろう。きっと自分から進んで毒の多いエリアへ隠れようと思うはず。
あの子ならどういう行動を取るかを考えながら、わたしの足は自然とフィンダムの奥地、病が蔓延する地へと歩んでいく…。
自分の背中から大きな棘が突き出して、三日がたった。
だんだんと考えることが億劫になってきたが、まだ思考力が残っているオレは、病に抵抗するように、泥の水を泳いで向こう岸に行った。べっとりと濡れた重い体で岸に上がり、ブルンブルンと体を振るう。
ああ、億劫だ。何もかも。だが、飯を、食いたい。何か。食べ物を。
のっそりと動き出すと、影の鳥がギャアギャア言いながらいっせいに襲ってきたが、無視した。こいつらは食べられない。相手をするだけ無駄だ。
まだ比較的飲める水が流れている川まで行くと、今日も今日とてリザードマン系の魔物が水取り合戦をしていた。水場が欲しいヤツはたくさんいる。ライバルが絶えないのだろう、ここのリザードマンは見かけるたびに戦っているように思う。
漁夫の利、というヤツに預かりたいな、と端っこで水を飲みながら様子を窺っていると……ニンゲンだ、という声が聞こえた気がしたが、無視した。
そんなバカなことがあるわけがない。こんな病の地に人が出入りすれば、それだけで病をもらうようなものだ。ありえん。
だが、あちらこちらからニンゲンだ、食い物だ、エサだ! と声が上がり、ピクシーと争っていたリザードマンたちまで動きを止めたので、そんな馬鹿な、と思いながら川の魚を一咬みで捕まえて顔を上げ、
絶句した。
せっかく捕まえた魚を落とし、ボチャン、と川に落ちた魚は血を出しながらも逃げていく。
「ぁ、」
ずっと靄がかかったようにはっきりしなかった思考に、まるで稲妻が落ちたように光が閃いた。
久しく、忘れていた、人の言葉を。唐突に思い出す。
「あ。に、り、ん」
視線の先にいる彼女は、左の腕から緑の棘こそ生やしていたが、オレと同じで、まだ思考力は健在のようだった。視線を彷徨わせていた彼女はオレに気づいたのだろう、獣のこの目には、彼女が嬉しそうな顔をしたのが見えている。
なぜ。
いや、なぜ、など、あの顔を見ればわかる。
偶然ではない。アニリンはオレを捜していたのだ。いなくなったオレを追ってきたのだ。穏やかな人の生活を捨てて。
リザードマンや影となったハーピー、毒に侵されたピクシー。すべてがアニリンという制圧しやすい彼女を食料と捉えて動き始めたとき、オレの心臓は久方ぶりにドクドクと鼓動を始めた。
四肢に血が行き届くのがわかる。
これまでぼんやりとしていた体が、毒の胞子が蔓延る大地を踏みしめ、これでもかと砂利に爪を食い込ませる。
アニリン。オレのアニリン。
(彼女はオレのものだ。手を出すことは、許さない)
ともに狩りをしたことなど、もう随分と昔のことのように感じる。それだけ長く離れていたような気もする。だが、アニリンの目配せは『自分が囮になる』という意味だとすぐにわかった。
魔物に怖気づいた…ように見せかけて逃げ出したアニリンを、我先にとピクシーが追いかけていく。続いて影となったハーピー。続いてリザードマン。
地上では動きが鈍くなるリザードマンは逃げ出したアニリンに気が向いていて、最後尾のリザードマンの喉笛を食いちぎったオレに気づきもしない。
硬い鱗が生えているリザードマンだが、腹と喉はやわらかいと知っている。オレが確実にリザードマンをやるなら喉しかない。
顔にかかる血が不快だが、ガマンしてやろう。
アニリンはうまくやる。
だが、素早く。確実に。彼女に危険が及ばないうちに。
喉笛を食いちぎりながらリザードマンを殲滅したあとは、アニリンを追うよりリザードマンの躯を貪ることにしたハーピーを除外して、残るはピクシーだ。
(オレが、この牙で、すべて、貪る)
枯れ木の太枝になんとか登ったアニリンを取り囲んでいるピクシーは、とにかくうるさく喚いている。耳障りなほどにギャアギャアと。
体毛が逆立つと同時にブワッと自分から胞子が吹き出すのを感じたが、気にせず、力を込めた四肢で地面を蹴飛ばし、ピクシーの一匹に背後から襲いかかる。
奴らはリザードマンのような鱗はない。喉笛でなくともいい。数匹手足をもいでやれば怖気づいて逃げ出す。
一匹の背中を脇腹まで爪で切り裂き、派手に鮮血を散らせたら、こっちに気づいた一匹の顔に爪を叩き込む。二足歩行とまではいかないが、立ち上がって前脚を使うことくらいオレにもできる。
三匹目は手でももごうと考え、カチン、と奥歯を噛み合わせて感覚を確かめていると、あっという間に仲間がやられたことに動揺したらしいピクシーどもが逃げ出した。仲間を担ぐこともしないで一目散だ。
ふん、と息をつき、血を撒き散らしながら喚いているピクシーの喉笛を前脚で踏み潰した。うるさい。
もう一匹は目を潰したが、這ってでも逃げていたため、面倒になって放置した。あの様では影の鳥につつかれて終わるだろうよ。
木の上から状況を見ていたアニリンがおずおずと顔を出す。
「おりて、いい…?」
「いい。おわり」
物言わなくなったピクシーを転がすと、彼女は頷いて太い枝から飛び降りた。
アニリンはまだ軽やかな動きができるのだ。片腕でも。病に侵されていても。…独りでぼんやりしていたオレとは違うのだ。
近づくのをためらうオレとは逆で、アニリンは迷うことなくオレに駆け寄って、病も毒も気にせずオレに抱きついた。
「やっと見つけた。遠かった…時間がかかったよ……」
「……、な、ぜ」
なぜ、病の地に来た。なぜ、オレを追いかけた。気づいていながら、問うてしまう。
アニリンは知っている笑顔を見せる。無理がなくて、ささやかで、それでも笑っている、あの顔だ。
リザードマンの返り血を浴びて汚れている、背中と言わずあちこちから緑の棘を生やしているオレに、笑いかけるのか。
(オレで、いいのか。オレが、いいのか?)
どうせ、病という暗い道しかないのなら。その道に誰も巻き込まずに殉じようと思っていたのに。決して誰も巻き込むまいと思っていたのに。
アニリン。お前は自分からこの道に落ちてきて、オレの頭を撫でるというのか。
「残りの時間が、少ないのだとしても。だからこそ、わたしがしたいのは、穏やかな暮らしじゃなくて。あなたと一緒に、過ごすこと、だよ」
血生臭くて、胞子を散らして、棘まで生やして。角が片方なくて、片目も潰れて。そんなオレでもいいと、アニリンは言う。そんなオレがいいのだと、アニリンは。
ガラでもなく片目が熱くなった。
オレがいいなどと。他の誰でもないオレがいいのだ、などと、言われる日がこようとは。
ぷいと顔を背けてのっそりと歩き出すと、慌てたようにアニリンがついてくる。「どこ行くの?」「ね、どこ」「あるの?」「ぁる」大神殿の方を顎でしゃくって、それから、さっき全滅させたリザードマンの躯から尻尾をちょうだいした。ここは案外とうまいから食えるのだ。「アニリン」「うん」アニリンに一つ預け、自分で一つ噛んで持ち上げ、アニリンが川の水を汲むのを待ってからその場を退散した。
占領していたリザードマンが消えたのだ。あそこはそのうち縄張り争いが激化するだろう。巻き込まれないに越したことはない。
片腕のアニリンに泳げというのはなかなか無謀な話なので、先に荷物とリザードマンの尾を離島まで運んで、アニリンには背中に掴まってもらう形で彼女を運んだ。完全に乗られるとオレも泳ぐのが難しいので、浮かぶアニリンをオレが引っ張っていく形だ。
離島にたどり着いた頃にはさすがにオレもへばっていたが、アニリンは片腕でもテキパキと枯れ枝を集めてきて焚き火を作った。小さな鞄から小さな包丁を取り出すと、さっそくリザードマンの尻尾を切り始める。
そんなアニリンをぼんやりと眺めて……パチ、と目が合った。
オレは表情を動かすことが難しい獣の顔だが、アニリンは違う。だからすぐにわかる。表情で、その気持ちが。
アニリンは安心しているのだ。オレという病と毒の塊がそばにいることに安堵している。
リザードマンの尾の輪切りを手際よく枯れ枝に刺して火にかざしながら、彼女が言う。「ねぇ、もういなくならないでね」と。唸るように「ああ」と返すと、今度はこう言われた。「ねぇ、わたしたち、最期まで一緒よ」と。ああ、と唸るようにこぼした視界を緑の胞子が舞う。
ああ、疲れた。何往復も泳ぎ、その前はリザードマンを殲滅し、ピクシーをやり……数週間ぶりに動き回ったせいだ。ああ、疲れた。
だが、目を閉じ、眠るには、惜しい。
(まだ、アニリンを、見ていたい)
この道は暗く、ただ一本で、逃れようのない奈落へと続いている。
そこに希望や救いなどという甘いものは落ちていない。
だが、夜に咲いて仄かに光る花のような。そんなささやかな光なら、ある。ここに。オレのそばに。
アニリン。
お前こそが、オレの最も大切な光。
そんなわけで、結構長くなってしまったアニリンシリーズですが、これにて完結でーーーーす!!\( ゚д゚ )/
とある方の絵を見てビビッときて書き始めたアニリンシリーズ。あの絵のようなラストになったかと言われると難しいところですが、アリス的には精一杯ハッピーエンドに持っていったつもりです…!
アニリンシリーズ、お気に召してくれたなら幸いです!
↑ ちなみにエンディングにこちらを聞いてました。二人はこの歌のように穏やかに暮らしたんだと思うのです
アリスの小説応援! にポチッとしてもらえると励みになります❤(ӦvӦ。)
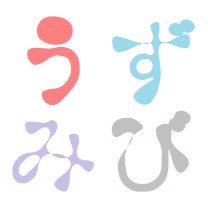






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません