30.喫茶店『ドラゴン』にて④
その日は土砂降りの大雨で、粒の大きな雫が絶え間なく地面を叩きつけ、空の暗雲はゴロゴロと嫌な音を立てていた。
「……嫌な天気だ」
窓の外を眺めて思わずこぼした言葉に紅葉が目薬を持ってくる。「まだ大丈夫だけどな」苦笑いしつつ彼女の手から目薬を受け取って、どこかピリピリとした刺激を伝えてくる目に一滴ずつ差しておく。
土砂降りの雨。おまけに雷が鳴り響く天気だ。雨粒が叩きつける窓の向こう、見える田舎の風景に出歩く物好きな人の姿はない。
そう、つまり、外は今人間でないモノが出歩くには絶好の環境となっている。
……ノアの喫茶店には弱っている何かがいて、毎夜のようにソレを狙う何かしらが湧き出ていた。なら、この嵐のような天気に乗じてやってくるモノもきっといるだろう。
テーブルに頬杖をついて嵐の景色を眺めながら、だったらなおのこと行かない方がいい、と思う。
そんな場面に出くわしたらぼくも魔術を使わざるを得ない状況になるかもしれない。そうなれば滝沢蛍としてカフェの常連客で通していた一般人の顔が剥がれてしまう。
先日のウィル・オー・ザ・ウィスプの件もある。彼らの無事は気になるけれど……。
カッ、と雷が鳴って視認できる稲妻が光の線として空を走った。一瞬窓に反射した自分の顔が映る。
「……、」
ばし、と手のひらで顔を押さえる。
なんて顔してるんだぼくは。
そんなに気になるのか? そりゃ、唯一の情報先がなくなりでもしたらぼくの仕事もおしまいだ。困るさ。だけどコレはそういうことを案じてる顔じゃないだろう。この表情は……。
(くそ)
セーターの上からコートを羽織り、足首まであるレインコートを着たぼくに、紅葉が冷ややかな目を向けて部屋の扉の前に立った。『また風邪を引かれるつもりで?』「…違うよ」透明なレインコートのフードを被り、ドアの前に立つ紅葉を見据える。
ぼくはどうにも、あのカフェに被害が及ぶことを見過ごせないようなんだ。
できることならあのカフェには何事もないままでいてほしい。あそこでノアの淹れたコーヒーを飲んでまた読書をしたい。
あの場所の平穏が、平和が、ぼくには過ぎたものだとしても。それが破壊されることをぼくは望まない。
この気持ちをなんというのかぼくは知らない。知らないけど、ぼくを突き動かそうとするこの感情のままに動きたいと、今は思う。
「ごめん、紅葉。行かないと。そこを退いてくれ」
『……………』
主たるぼくの命令に紅葉は逆らえない。そうできている。どれだけ外見が人間にそっくりでも彼女は機械なのだ。
一歩横にずれた彼女のそばをすり抜けてアパートを飛び出し、バケツをひっくり返したような雫が叩きつける中、泥に足を取られながら走る。走る。走る。
雨で視界が利かない。まるで煙のように雨が立ち込めている。不自然なほどに。
ああ、そうだ。不自然だ。あまりに不自然だ。この土砂降りの大雨も、他の音をかき消すように鳴り続ける雷も、何もかもが不自然だ。
走り抜けた砂利道の先にようやく喫茶店のぼんやりとした輪郭が見えたとき、見慣れた店が黒くずんぐりとした二足歩行の何かに囲まれているのがわかり、歩調が緩む。
それも一瞬で、ぼくは右のポケットから木彫りのルーンを引き抜いていた。

引き抜いたルーンを空へと放りながら、型も法則も無視して自分の魔力にただただ命じた。『あの店を守るように』と。
パン、と弾けて粉々になったルーンはぼくの魔力を結界へと変換し、店に押し入りそうだった黒くずんぐりとした何かを弾き飛ばした。
魔力の出所を察知して何体かのずんぐりとしたモノがこちらを振り返る、その間に左のポケットに入っていたルーンを引き抜く。
これでもう予備はない。だけど知るものか。
(撃ち抜け)
ルーンに込めた魔力で生成できるだけの魔力の弾丸で店を取り囲むモノを撃ち抜く。肉を抉る。頭を吹き飛ばす。黒い肢体に穴を開ける。
倒れた仲間を見て獣が咆哮を上げるが、うまい具合に鳴り響いた雷の音に紛れて、周囲はこの異変に気付かない。
銃を撃つ要領で魔力の弾を撃ち続け、尽きた。パン、と弾けて粉々になったルーンが雨に落とされていく。
アレは猿に似ているけど、猿よりももっと面倒な奴らだ。
オーガ。あるいはオーグル。日本で言うところの鬼は、毛に覆われた顔で二足歩行し、賢いものは言葉も喋るという。ロンドンなど街で見かけることはないものの、田舎や炭坑では時折悪さを働くとも聞く。それがこんなにも。
悪鬼として知られるオーガには諸説あるが、ぼくが目の前にしているモノは身長が二メートルほどあり、黒くずんぐりとした毛が全身を覆っている。雨で濡れそぼった黒い毛の中にギラギラした目と赤い口が見えるだけで、詳細は雨に煙っていてわからない。
「よぉし、久しぶりに本気を出そうじゃないか」
レインコートの腕を突き出して今潤沢で困らない資源、水を選択。カフェからぼくへと狙いを変えたオーガの群れに魔力で圧縮し刃にした水、ウォーター・カッターを放つ。
切れ味が良すぎるから刃が砕けるタイミングをぼくが判断しないとならないのが負担だけど、これ以上ないエコな武器だ。
ゴロゴロと頭上で鳴り響く雷に向けてもう片腕を突き出す。「仲間外れになんてしないさ」鳴り響く雷鳴に意識的にここへ落ちるように誘導をかけ、カッ、と光り轟いた稲妻をコントロールして複数のオーガの頭上へと落とす。これもコントロールに苦労はするが、効果は抜群だ。焼け焦げたオーガが数体、泥の地面に倒れて動かなくなる。
このくらいのレベルのモノなら自然の力だけで充分。ぼくはそれをうまく誘導すればいい。どれもゼロからイチを生み出す作業じゃないから、そこまで魔力の負担はない。
けど、作り出した結界の方が長持ちしなさそうだ。さっきからバンバンと容赦なく殴られ続けている。急ごしらえで魔力もそこまで注いでいない簡単な結界だ、あまり力をかけられると解けてしまう。
(彼らが滅びるのが先か、ぼくの魔力が尽きるのが先か。さあ、勝負だ)
圧縮した水の刃を放ちオーガを切り刻み続けるぼくの横に、カフェの窓を開けて外へ飛び出してきた人影が一つ。
あっという間にずぶ濡れになったシリルは邪魔そうに自分の髪をかき上げると、一眼でぼくを睨み見た。もう一眼はほんのりと光っている。
「背格好がどっかで見たヤツだと思ってたが。お前、駅のときのKだろう」
「はは。ご明察」
さすがというか、シリルは慎重に動いていたぼくのことをそれでも疑っていたらしい。確かに背格好は誤魔化していなかったけど。「だっせェ服のセンスが同じなんだよ。そこも変えとけ」「そんなに…?」こんな状況だというのに思わず自分の服装を見下ろしてしまう。今日はセーターにジーンズだけど、そんなにダサいのかな…。
魔術的なもので両手にナイフを握ったシリルが迷うことなく飛び出していくから、逆にぼくが慌てた。ウォーター・カッターがあるっていうのに迷いがなさすぎるだろう。
間違っても彼を傷つけてはならない。ぼくの仕事の大事な情報源だということもあるけれど……彼が怪我をするときっとノアは悲しむだろう。もしかしたら、ぼくが怪我をしても、悲しんでくれるのかもしれないけど。
ぼくの水の刃とシリルの人間離れしたナイフ捌きにより、オーガの群れがカフェに被害を出す前になんとか殲滅することに成功した。
ぼくは途中からはエネルギー切れを起こしそうだった結界の補強に意識を割いていて、オーガの処理はほとんどシリルに任せていたけど、問題なかったな。
「はー、」
絞り出していた魔力がついに途切れて、安全を確認する前に泥の地面に膝をつくどころか座り込んでしまう。
本来なら結界って、複数人できちんとした準備をした上でやるものだ。それか、そういう専用の道具に頼って簡易手順を踏んで張ったりとかね。一人で即席の結界を張ってここまでもたせるのは魔力的にも厳しい。疲れた。本当に疲れた。
人間離れした動きを見せていたシリルもやはり疲れたのだろう、左目の輝きが失われるのと同時に彼も止まった。「ゲホ」無傷とはいかなかったのだろう、背中を押さえて咳き込んでいる。
「大丈夫かい」
「掠っただけだ。そっちこそ、魔力切れか」
「結界はね、即席のものを維持するのは大変なんだ。念入りな準備をしてこその代物なんだよ……」
レインコートが台無しになるのも構わず、ぼくはそのまま背中から泥だらけの地面に倒れた。少しマシになった雨がぽたぽたと顔を叩く。
仕事的に考えれば、ぼくのこの突発的な行動は失敗だ。
冷静さを欠いて衝動的に動いた結果、ぼくは喫茶店を救うことはできたかもしれないが、そこで築いた信頼や立場を失った……。
魔力不足でどこかぼんやりする頭でノアはどんな顔をするだろうと考えていると、カラン、と喫茶店のドアのベルが鳴る音が聞こえた。「シリル…と……あれ」足音に、彼の声がする。
傘を差したノアはぼくのことを覗き込んだ。手にはシリルに被せる予定なのだろうタオルがある。「あなたは…」どんな顔を向ければいいものか、ぼくは苦笑いのようなものしか浮かべることができない。
「ソイツは魔術師だよ。オレらに探りを入れるために喫茶店の常連を装ってた」
シリルは容赦なく言い放った。ぼくへの配慮は一切ない。
ノアの表情にはきっと落胆の色が浮かぶだろうと思った。苦労して経営している店にようやく常連ができたと思ったら違ったのだ。彼はぼくに失望するはずだ。騙されていた、と思うはずだ。
けれど、彼が浮かべた表情は予想と少し違っていた。
ぼくへと手を差し出す彼は、残念だというように眉尻を下げてはいたけど、それだけだった。「とりあえず、起きてください。また風邪を引いてしまいますから」「……、」伸ばされた手を掴んで体を起こす。
魔力切れとレインコートを無視して入り込んだ泥と雨で体は冷たくなってきていた。
だけど、握った彼の手だけはあたたかくて、長いこと触れていなかった人の温度に不覚にも涙が落ちた。
………今日が雨で助かった。
ぼくは泣いてない。これは少しあたたかいだけの、ただの雨だ。
喫茶店ドラゴンで匿われている金の竜が死にそうなほどに弱っているため、魔的なモノが毎夜のように湧き出てきてそれを処理していたシリルとリリー
今度は堂々と昼間、悪天候に紛れてやってきた猿のような鬼のようなモノの集団に喫茶店を襲撃され、店の被害は免れないだろう、というピンチのときにケイが駆けつけました
まだまだ続くぞー!
アリスの小説応援! にポチッとしてもらえると励みになります(ӦvӦ。)
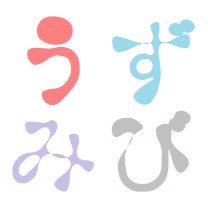






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません