13.忘却の呪
ありがとう
ごめんね
さよなら
そう言って、真っ赤なワンピースを翻し、姉は、飛んだ。跳んだ。翔んだ。
軽やかに。三階の部屋の、屋根裏の、決して低いとはいえない高さの窓からふわりと、まるで風と遊ぶようにして一瞬だけ彼女は浮遊して……落下した。
鈍く、耳に届く、衝撃音。何かが地面にぶつかった音。
それまで姉と一緒におままごとをしていたわたしの手から、おもちゃの包丁が落下してカランと乾いた音を立てた。
おねえちゃん?
彼女をそう呼ぶ自分の声はひどく掠れていて、床に座り込んだまま動けなかった。
姉が落ちた。どうしてかはわからないけれど、落ちてしまった。
人を呼ばなければ。助けなければ。窓に走り寄って、誰かって、声を上げなければ。
ちっとも力が入らない膝で、這いつくばって窓辺に寄り、白い陽射しと青い空に目を細めながら、開け放たれたままの窓の枠を掴んで体を引きずり起こす。
どうにか外へと顔を覗かせると………姉が、落ちていた。ひしゃげていた。潰れていた。
生きている人間はああはならない、そんな方向に腕と足が曲がっていた。
姉のワンピースは相変わらず真っ赤で、その赤から、さらに赤が流れていた。
…悲鳴が聞こえた。誰か、お手伝いさんが駆けつけて、姉の姿を見て悲鳴を上げたのだろう。そう思った。
でも、違った。
部屋に飛び込んできた母に引き寄せられて初めて、わたしは、自分が潰れた声で悲鳴を上げ続けていたことに気がついた。泣きながら叫んでいることに、気がついたのだった。

陽射しを避けるために分厚いカーテンを引いたままになっている暗い部屋で身を起こすと、暗闇の中で、よく知った顔がこちらを見ていた。…姉だ。
(今、あなたの夢を見ていた)
全身が真っ赤な姉は、物言わず、ただじっと、目と思われる空洞でわたしのことを見つめている。
物言わぬのに、物言いたそうに(わたしがそう感じるだけかもしれないけれど)わたしを追う空洞は、やがて溶けて、わたしの服になる。
血でできた真っ赤な服を纏ったわたしは、ブーツを履いて、薔薇の描かれた日傘を持って、光の射し込まない部屋を出た。
シンと静まり返った家にはおよそ人の気配がない。
隣の部屋も、向かいの部屋も、ただただ静寂だけが居座っている。
わたし以外に音を立てるものがない世界。
それでも、軋む階段を下りて階下に行くと、おじい様がいる。
生者の気配のないおじい様は、暖炉の前の揺り椅子に腰かけて、今日も何かの魔術を編まれていた。
「起きたかね」
「はい。おじい様」
暖炉の燃え盛る炎だけが明るい部屋で、わたしは揺り椅子の横で膝をついて彼に目線を合わせた。「今日は仕事がある」「はい」「内容を、憶えているかね」「はい」「復唱を」「はい。奪われた価値ある骨董品を回収します」「よろしい。モノはなんだったね?」「はい。機械式の懐中時計です。ハンターケースにルビーがはめ込まれています」「そうとも」それまで手元から目を離さなかったおじい様が、わたしを見た。落ちくぼみ、筋肉の削げ落ちた骸骨の顔で、三日月のような口でニタリと笑うその顔が…わたしは、苦手だ。
「なるべく速やかに回収しなさい。目立たぬように」
「仰せのままに」
頭を垂れたわたしは、静かに立ち上がって一礼し、おじい様のそばから離れた。
彼はそれきりわたしから興味を失ったようで、手元で編み続けている何かの魔術に意識を落としていった。
外界の光というものをできるだけ遮断した暗い屋敷から、重く冷たい扉を押し開けて外に出ると、光が刺した。わたしを、刺した。鋭く慈悲のない白で。
目を細め、外界の眩しさに視界が慣れるのを待つ。
………目が慣れて、見えた世界は、灰色だった。
姉を亡くしたあの日から、わたしの世界はずっと、灰色だ。
血の色以外、わたしには色の識別ができない。あとは白か黒か、灰色か。そのどれかだ。
手にしている日傘を差し、コートの内ポケットにいつも入れているナイフで親指を少しだけ切る。赤い血が溢れ出し、玉となってぷっくりと肌の上にのる。
(追跡を、開始)
決まりきった呪文を唱え、肌の上でこぼれそうになっている血の雫を落とした。
ポタ、と地面に落ちた雫が地に沈み込み、やがて浮き上がり、赤い染みとなって地面の上を滑るように移動していく。わたしはそれを追いかける。
おじい様が言うには、ルビーがはめ込まれたその懐中時計は呪術的にそれなりに価値のある品で、仕入れにいった昨日、スられてしまったらしい。
人混みの中で、おじい様が得意な人を呪う魔術を繰り取り返すわけにもいかず、おじい様は懐中時計に追跡の魔術のための目印を刻んで、犯人の男を見送った。
運がない人だ、と思う。おじい様がじゃない。よりにもよっておじい様から盗みを働いたその男が、運がない人だと思う。
他の誰かだったなら、こんなことにはならなかったのに。
地面を滑っていく血の染みが路地裏に入る。暗く、不清潔で、毛布を被って蹲っている人間がいる狭い空間。
デコボコの煉瓦の上を滑っていく血の染みが、とある男の前でピタリと止まった。コイツだ、と残して血の染みはただの黒ずんだ汚れに変わる。
周囲に人気はなかった。この男はよりにもよって、こんな路地裏で、一人でいた。
ああ。本当に、運がない人だ。
わたしが目の前で立ち止まったことに気づき、帽子を目深に被った顔を上げようとした男の首に、赤い刃を突き立てる。
音を、声を出す暇を与えず首を刈り取り、噴き出す赤を片手を掲げてすべて吸収しながら、もう片手で男の懐をあさった。…あった。懐中時計。ルビーもそのままだ。分解しようとした形跡があるけれど、魔術を知らない男には手に余る代物だったらしい。
(よかった)
これで、おじい様に折檻されずにすむ。
体中の血液を失い乾いたミイラのようになっている男だったモノをエコバッグに詰め込み、人目につかない道で家に戻った。
家を出たときと同じ、揺り椅子に腰かけて何かの魔術を編み続けているおじい様の隣に膝をついて目線を下げ、取り戻した懐中時計とエコバッグを見せる。「見られてはおらんかね」「はい。誰にも」「よろしい」揺り椅子のそばにあるテーブルにエコバッグと懐中時計を置いて一礼し、部屋に戻ろうとして、「ドール」と呼ばれて足が止まった。
ドール。人形。
それは、おじい様がわたしを呼ぶときの言葉。わたしの名前ではないけれど、もう、わたしの名前のようなものだ。
この世界に、わたしの名前を呼ぶ人はもういない。
「はい。おじい様」
揺り椅子のそばに戻って両膝をつく。「新しい仕事だ」「はい」わたしに拒否権はない。わたしはドール。おじい様の人形だから。
すっかり枯れ枝のようになった細い足で、おじい様が床を叩くと、影から伸びてきたタールのような黒いモノがそばにやってきて、ビヨンと伸びて、何かの形を取った。…人の形。男の人、だと思う。顔立ち的に、アジア人。
「ノア・ステュアート・オブ・ダーンリーという」
「…はい」
「お前はこの男に取り入りなさい」
「…?」
それは、おじい様らしからぬ言葉だった。
取り入る。その男が邪魔なのなら、命を刈り取った方が早いのに。なぜだろう。
訊くことはできず、わたしは、ただ、困惑した。
取り入るだなんて、やったことがない。ずっとドールと呼ばれ続けて、ドールらしく、感情を表に出さないような生き方をしてきた。おじい様に求められる生き方をしてきた。今更、人間らしく誰かと接するなんて、わたしには…。
おじい様は、ずっと手元で編み続けていた何かの魔術を、完成させていた。「案ずるな。儂が手を貸してやろう」「…はい」じわり、と背中に嫌な気配を感じた。わたし、冷や汗をかいている。
おじい様の手元で妖しく光る小さな陣が、わたしの額に、押し付けられる。
瞬間、頭が割れるほどの激痛に、思わず叫び声を上げていた。
それでも抵抗はできない。おじい様には逆らえない。わたしはドール。おじい様の人形だから。
(痛い、痛い、痛い、いたい、いたい、イタイ、イタイイタイイタイイタイイタイ)
あまりの苦痛に視界すら飛んで、わたしは、何も、見えなくなった。
すべてを忘れなさい
今この瞬間だと思うそのときまで、お前はただの娘だ
ただ、最後に、おじい様の、暗く澱んだ、嗤った声が、した。
またもやお久しぶり更新となってしまいました(´・ω・`) いろいろと忙しかったのです。。気付けばもう今年も終わる!!
そんな中で13話め! 新しい登場人物が追加です!
また一波乱ありますよこれは…!
応援! にポチッとしてもらえると励みになります❤(ӦvӦ。)
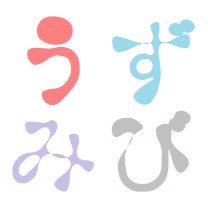






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません