9.光の宿意
馬鹿な親がいた。
頭が良くないという意味でもそうだし、お人好しという意味でも馬鹿な、両親がいた。
頭が良くないくせにお人好し。およそ出世できない、面倒事だけを体よく押しつけられる、それを笑って是という親がいた。
別に、自分を通して人に嫌われるのが怖い、なんて人たちではなかった。ただ、絶望的なまでに、人が笑うことを是とする人たちだった。その笑顔の裏にどんな顔が隠れているのか、想像もしない、大人になったのに純粋さを忘れていない、珍しい人たちだった。
そんな馬鹿でどうしようもない二人の親のもとに生まれたオレは、当然、馬鹿に育った。
人に手を差し伸べることに迷いなどしなかったし、笑顔の裏なんて疑ったこともなかった。
人に親切に、いつも笑顔で。
天使が存在するとしたらこういう心を持っているんじゃないか。そんな親のもとで育てば、子供だって自然とそうなる。
今となっては、それは懐かしい、遥か昔の話。
………およそあたたかさしか知らなかった心が、砕け散ったのは、馬鹿な両親が限りなく事故に近い形の悪意でこの世を去ったときだった。
今でもハッキリと憶えている。
ガラスでできた透明な心が、夜の闇を流し込んだように黒く淀んだことを。
言葉にならない衝撃で、ガラスの心にヒビが入り、泥みたいに汚いものが溢れ出る、あの音を。
あんなに無害で、善意に溢れていた、傍から見ればただ馬鹿なだけの人たちが。人間としてどうか、と思うほど、良い人たちが。それでも、世界の悪意に、個人の横暴でしかないテロという悪意に、命を奪われる。
善であることは無意味だ(世界は善を評価などしない)。
手を差し伸べることは無意味だ(どれだけ心を配っても、返されるものなどない)。
愛に愛は還らない(戻ってくるのは、ただの悪意)。
両親の残骸が入った棺を前に、無感情なロボットがただ作業的に両親を埋葬していく様子を見ながら、思った。
長いものに巻かれよう、と。世界に溢れる軽やかな悪意に身を任せて、泥のようにしつこい感情の群れに浸かって、流されるまま、楽に生きよう、と。
オレは、純粋無垢だった子供を捨てた。
両親のようにはなるまい。そんな馬鹿みたいに命を終えたくはない。
(そんなのは本当に、損だ)
この世界では善意より悪意が勝つというのなら。オレだってそうしよう。
両親のようにはなるまい。絶対に。あんな惨めな最期だけは、絶対に。

古い、銃身に『破壊』の呪詛が刻み込まれたリボルバーの銃を片手に、オレはノアと向き合っていた。
長身ともいえない痩躯に、イギリスではあまり馴染まない黒い髪。
パッと見たところアジア人にしか見えないコイツは、大学の同級生で、ノア・ステュアート・オブ・ダーンリー。すでに没落したとはいえ、過去イギリス貴族として名を刻んだステュアート家の長男だ。
今はもう一般家庭と同じ暮らししかできていないと言われているステュアート家が、ついに血を捨て、アジアの女と結婚した、あいつはその子供だ。そう囁かれているのを何度となく聞いてきた。
「ドラゴンを出せ、ノア」
二度目になる言葉を投げるが、ノアが懐に隠した金色のドラゴンを取り出す素振りはない。
オレの背後では、ジリ、ジリ、と少しずつ呪詛がドラゴンの命を焼いていた。
……直接手を下すまでもない。指示通りに落命の呪いの時計を早めたんだ。ドラゴンはもう五分で炭になるだろう。
かつてのクラスメイトを前に、オレは嘆息して銃口を上げた。「なんで出さない」「…差し出したら、ドラゴンがどうなるかくらい、僕にもわかる」ああそうかよ。面倒な奴だ。オレは親切で言ってやってるっていうのに。
「いいか? ノア。そのドラゴンは呪詛で命を削られてる。もう終わりが近いが、そりゃあ苦しいもんだろうさ。その苦しみをオレがこの銃で終わらせてやろうって言ってるんだ。わかるだろ?」
「わからないよ」
キッパリと、あいつは言う。旧式とはいえこっちは銃っていう絶対有利な道具を持ってるっていうのに、まっすぐこっちを見てやがる。
「この子が何をしたっていうんだ」
「さぁな。事情は知ったこっちゃない。オレは指示されただけだ」
「………それだけで。君は罪のない命を奪うのか?」
まっすぐな目で言われて、イラついた。
ノアのシャツの間から蒼い瞳でこっちを見ている金の竜に迷わず銃口を向け、発砲する。
この銃に刻まれている破壊の呪詛は、動植物として優秀で丈夫な竜の鱗を砕けるよう刻まれたものだ。これを食らえば小さなドラゴンなんてイチコロだろう。
これで仕事は終わり。そう思った。
だが、出血したのは竜ではなく、竜を庇ったノアの腕だった。「…っ」呪詛の効果で相当の痛みのはずだが、ノアは声も上げずに呑み込んだ。痛みも、苦しみも、熱も、すべて。
運悪く貫通しなかった弾は、ノアの体内で暴れ回ったに違いない。だが、それでも奴は膝をつかず、まだ立っている。そして、まっすぐな瞳でこっちを見ている。
「……なんで、そこまでする。ドラゴン相手に」
問うたオレに、ノアは唇の端を上げて、笑う。痛みでノアの顔面は白い。それでもあいつは笑うことを選ぶ。
「そう、だなぁ。うまく…言えないけど。色のない、日常に。舞い込んだ。僕の、光だから…かな」
笑ってそう言うその顔に、ザザ、と頭に映像が走った。
ああ、笑っている。
(誰かが、笑って。あれは)
瞬間、ゴリ、と疼いた左目を掌で押さえる。
……長引かせれば、マズいのはオレもか。そうなる前に、さっさとドラゴンを。
疼いて出血する左目に構わず、赤い色で濁る視界で銃を構える。その視界で、あいつは驚いている。「シリル、血が…」阿呆か。お前だって腕がダメになったろうが。まぁ、それはオレのせいだけど。
これ以上ノアに迷惑はかけまいと殊勝なことでも思ったのか、懐から飛び出して小さな体で飛び去ろうとする金のドラゴンに銃口を向ける。
左目は血で濁っているが、正確に目標までの道筋を教えてくれる。
これで終わりだ、と引き金を引く、刹那。迷いのない動きで射線上に飛び出したノアに、左目の疼きが増した。せいぜい伝うほどだった出血量が、今やボロボロと涙を流すみたいにとめどない。
(なんでそこまでする、)
このまま、オレが引き金を引けば、お前はまた痛みと苦しみに身を焼くのに。
乾いた発砲音に、肩を貫かれたノアの体が弾けた。相当の衝撃に、痛みに焼かれながら、あいつはそれでもまだ立っている。
ジリ、ジリ、と、背後では呪いの針が進む音がする。焦げ臭い、命が燃える臭いも。
(ああ、オレは、何をしてるんだっけ? ダチを撃って、目から血ぃ流して)
モゾモゾと、左目が疼いている。眼球が自分から動き出しそうなくらいの異物感に吐き気がした。実際、吐いた。…吐いたのは胃液じゃなくて血だったけど。
『呪詛に必要なのは、悪意だ。
ただ人を傷つける心。ただ人を貶める心。純粋なる、悪なる意思。
正義など捨てよ。善意など捨てよ。悪意を持って呪いを成せ。世界はそこらじゅう悪意で満ちている。
ただただ呪え。呪え。呪え。呪え。呪え。
それで呪いの時計は終わりを告げる。
だが、気をつけよ。
ドラゴンをも屠る強力なる呪いだ。もし、心ない善意など抱こうものなら、その左目はお前を……』
血を吐いて膝をついたオレに、腕と肩を撃ち抜かれ、倒れてもおかしくないノアがふらつきながら寄ってきた。「シリル…」その顔はオレが与えた痛みに歪んではいるが、明らかに、オレを気遣っていた。お前を、撃ったオレを。ドラゴンを、ただただ呪って終わらせようとしたオレを。
ごぼ、と喉をせり上がった血を吐き出す。
『心ない善意など抱こうものなら。その左目は、お前を呪うだろう』
氷のように感情のない老人の声が頭の中で響いている。
ああ、そうかよ。…そうかよ。
やっぱり、オレには向かなかった。オレは、ダメだった。長いものに巻かれようと泥にも闇にも、肥溜めに等しいもんに身を浸してきたのに。クソが。
せめて、最期のあがきにと、震える手でポケットから聖遺物を取り出す。大金叩いて手に入れた、一度だけ身を護るコインだ。「の、ぁ」「うん」「どらごんに、これを、やれ。はやく」「え?」「は、ゃ」左目は今やオレの意思も制御も外れてめちゃくちゃな動きをしている。眼球がグルグルと回っている。…ありえない光景が見える。両親の棺。雨の共同墓地。誰もいないそこでオレは一人ロボットに指示を出して両親を埋葬している。
オレも、ああなる。
今度は誰もいない。オレを見送る奴は誰もいない。
なんて、虚しい、最期。
ついに右目からも出血し、世界は完全に赤く染まった。耳障りな笑い声までする。馬鹿だなぁ、馬鹿だなぁ、そう言いながらオレを嘲笑っている。
あのコインは、最後の手段で、お守りでもあった。それをやっちまったんだ。…もう、どうしようもないさ。
それに、これでもいいとも思う。
虚しい、最期になったが。こんなオレが生き残るより。未だ輝きを失くさないお前が、生きろ。
赤に染まる視界で、金色が輝くのを、最期に見た気がしたが、確かめる前に、オレの世界は途切れた。
ああ、認めよう。
地味で、特徴も特技もさしてない、アジア人の見た目のお前を『友人』として付き合ったのは、お前の善性に憶えがあったからだ。
それはかつてオレが持ち合わせていたものであり、失ったもの。もう二度と手にすることのない、かけがえのないあの輝き。
長いこと泥に浸かって二度とキレイになどならない汚れきったオレと違い、お前の心はまだ曇っていなかった。どこかでひび割れ、欠け、危うい輝きはあったが、まだ光っていた。
それを、くだらないイジメで失くさせるのは、惜しいと。そう思った。
だからオレが友達になることにした。あいつを度々巻き込んでは迷惑だろうことに連れ回した。それであいつの気が少しでも紛れれば良いと思った。こんな生活もまぁ悪くないと、そう感じて生きてくれればいいと思った。
そのためなら、いくらでも馬鹿をしよう。
だって、さ。ただ失くすには。ただ色褪せるには。お前の持っているものは、美しすぎるよ。
(ノア。あいつの笑った顔は、あの二人が笑った顔に、そっくりだ)
どうしようもない馬鹿な両親。世界の悪意に呆気なく奪われた善意たち。
オレは、彼らが、ただ、好きだった。
9話め! シリル・キーツという人についてでした!
詳しく語るとアレコレありますが、まぁまたまとめてどこかでお話できればって感じです( ˘ω˘ )
忘れないうちに! また書きにきますね!
応援! にポチッとしてもらえると励みになります❤(ӦvӦ。)
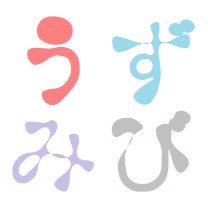




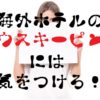

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません