5.ロンドンの街で②
ついていくの言葉のとおり、シリルはセント・パンクラス駅まで徒歩で行く僕の斜め後ろを歩いたり隣に並んだりしながら僕についてきた。…駅までくれば諦めて帰るかもしれないと思っていたんだけど、僕の読みは外れてしまったらしい。
駅前の喧騒のざわめきと立ち並ぶ立体映像の表示が視界に騒がしい中、僕は溜息を吐いた。
改札を抜ければさすがの彼も諦めるかもしれないけど、それでは買い物をすませることができない。
僕は彼を諦めさせることを諦めて、駅に向かっていた足で方向転換した。「お? どっか行くのか?」シリルは遅れることなく僕についてくる。「ちょっとね。買い物がしたいから」答えながら端末でチェックをつけた店までの案内を立体表示させる。
道案内に従って歩く僕に、シリルは無遠慮に僕の端末を覗き込んだ。
「なになに。ロゴス? これ、アウトドアの店じゃないか?」
端末には彼の言うとおり、『LOGOS』までの道案内が表示されている。
ロゴスはアウトドア全般を取り扱う日本発祥のブランドで、しっかりした作りのわりに他ブランドに比べて値段が安めで設定されていることで世界にまで進出したブランドだ。アウトドア初心者が入門として購入するのにちょうどいい価格設定になっている…と、イギリスに来るまでは日本で生まれ育った母に聞いた気がする。
「ノアってアウトドア好きだったっけ? どっちかっていうとインドア派かと思ってたけど」
「まぁね。パソコンをいじったり本を読んでいる方が落ち着くよ」
「じゃあなんでロゴス? 新しく趣味でも始めるとか?」
「まぁ、そんなところ。学校を卒業したらスポーツをする機会も減ったからね。社会人でも体力は作らないと」
もっともらしい嘘を並べつつ、僕はチラリと彼の表情を盗み見た。「なるほどねー。田舎はジムもなさそうだしな」彼はとくに僕を疑っているふうではなく、どちらかというと感心しているようにも見えた。もう少しこの話題を続ければ、きちんと本物になりそうだ。
「そういうシリルは?」
「オレぇ? そうだなぁ…付き合いでバスケとかサッカーとかするけど、とくに楽しいとも思わないんだよなぁ。ジム行くほど体力筋力に困ってるわけでもないしなー」
彼はヘラヘラ笑ってチェックのつば広帽を被り直した。
程よく着崩したシャツ、ニットのベストにだらしなくない素材のチノパン。ありふれたイギリス人の顔立ち。
騒がしい立体映像とセント・パンクラス駅を背景にした彼は、僕のなりたいものそのものに見えた。

店に入ってもシリルが帰る気配がなかったので、僕は否応なく彼を連れたまま買い物をすることになってしまった。
お目当ては靴と手袋と水筒だ。それだけあれば、他はとくに必要ない。
それなのに、シリルはいちいち店員を呼んで初心者にはどれがいいのかとか訊いていたし、放っておいてくれていいのに「帽子はあるのか? 山って結構日焼けするらしいぞ」とか「熊よけのスプレー! 熊は出なくても野生動物とは遭遇するだろうし、あった方がいいんじゃないか?」とか、アレコレ指摘してきて、それに受け答えしつつ買い物をすませるのに結局一時間もかかってしまった。
なんだかどっと疲れて(思えば、一人で喫茶店で黙々と作業していることが多いから、こんなにたくさん喋ったのもかなり久しぶりかもしれない)僕は目についたカフェで休憩することにした。
端末で帰りの電車の時刻を確認しつつ、二十分ほどはカフェにいられるはずだと計算して、今どき古風なベルのついた木製のドアを押し開く。
こういった昔ながらの雰囲気の店に惹かれてしまうのは、自分が継いだ店と似た雰囲気であることに安心感を覚えるから、かもしれない。
あとは、ほら。同業者として勉強になる部分があるかもしれないし。どうせ利用するなら味の保証がなくてもこういったお店にしたい。
シリルは当然のように僕についてきて、テーブル席に座った僕の斜め向かいに落ち着いた。
カウンターから注文を受けにやってきたのは落ち着いた雰囲気の老人だった。
「ご注文は?」
「ホットコーヒーで」
シリルはメニューを見もせずにとりあえずどのカフェにでもあるだろうドリンクを頼んで被っていた帽子をテーブルに置いた。
僕はメニューを取り上げて、今どき昔風の紙を使ったメニューに感心しつつ「僕もホットコーヒーを。それから、サンドイッチをください」とオーダーして、一度はメニューを置いた。
店主だろう老人がカウンターの奥に行ってから、改めてメニューを眺める。…そんな僕をテーブルに頬杖をついたシリルが見ている。
彼は昔から観察癖がある。そのとき目を逸らしもせずにじっと相手を見つめるから、いやでもそれがわかる。
「ノアさぁ」
「うん」
「どこで働いてんだっけ?」
何を言うかと思えば、そんなことか。
僕は少し躊躇した。彼に話すべきか、適当にごまかすべきかを。
今どき田舎にこもって、しかも喫茶店を切り盛りしているなんて言って、肯定された試しはない。
親にでさえそうなんだ。大学時代の友人、といえるかもしれないシリルに話したとしても、きっと笑い飛ばされるだけだ。
けれど、なんとなく。この友人が僕の心配をしているような気がして、適当にごまかそうとして開いた口から言葉が続かなかった。
逸らすことなくまっすぐにこっちを見つめる瞳に、昔のことを思い出した。
シリルの観察眼が一番に発揮されるときを僕は知っている。
学生時代。彼は燃え上がるような情熱を見せつけるときが何度かあった。
彼の中にはおそらく触れない方がいいスイッチみたいなものがあって、ひとたび押されてしまうと、彼は制御ができないくらいに凶暴になる。それも『正しさ』ゆえに。
簡単に言ってしまえば、彼は極端に曲がったことや極端な悪が許容できない人間で、それを正すためなら喧嘩もナイフも厭わない。
その根底には、極端な悪や間違いによって傷ついた誰かを案じる心がある。不条理や理不尽を許せないと思う彼の良心がある。
誰の中にも存在するだろうその善の心が、彼の場合、少し激しく燃え上がっている。そんなことを僕はようやく思い出した。
「…たぶん、笑うよ」
「おかしな話ならな」
僕は、どう笑えばいいかな、と考えて、精一杯笑ってみせたけれど、きっと不器用な笑い方をしていただろう。「祖父の喫茶店を継いだんだ」一言、サラリと、笑って言うだけのことが、なかなかうまくできない。
シリルは笑わなかった。クスリともしなかった。彼はきっと今どき喫茶店なんかと笑うだろうと思っていた。…いや、どうだろう。学生時代の彼を思い出したせいか、クスリともしないでこちらを見つめる彼を意外だとも思わない。彼には二面性があることを僕は思い出した。
「自分で選んだのか」
「まぁ、ね。祖父が…亡くなって。喫茶店をたたむって父が言い出して。それをどうにかしたくて…」
「そうか。…辛くないか?」
僕は、そう言う彼の瞳の奥に燃える感情を見た。本当に、燃えているように、彼の瞳の奥で何かが煌めいていた。
そこで、コトン、とテーブルにコーヒーカップが二つ置かれた。僕が頼んだサンドイッチも一緒だ。
彼の視線がコーヒーに移って、次に僕を見たとき、彼の瞳に炎はなくなっていた。
「どうかな。よくわからない。辛い…のかもしれない」
カップを引き寄せて、まずは一口、味わって飲む。自分の淹れるコーヒーとの違いを確かめながら。そのあとは、疲れを癒やすための糖分として角砂糖とミルクを入れる。
「辛いかもしれないけど、大丈夫だ。自分で選んだ道だからね。今は少し、違う光も見えているし」
思い浮かぶのは金色の竜のことだ。
あの存在が今後店に、僕に、どんな影響を与えるか、まだ未知数だ。
金色の竜という強すぎる光によって店も僕も灰になるかもしれないし、夜に欠かせない月のようにしっとりとした灯りとなってくれるかもしれない。
僕は竜がくれた変化を受け入れた。竜がくれた日常の変化に、応えようともしている。だからロンドンまできて、アウトドアの店に行って、帰りの電車を待っている。そのことを悪いことだとは思わない。この今が、悪いものだとは思わない。
「だから、僕は大丈夫だと思う」
ふーん、とぼやいたシリルはコーヒーを一口すすると、苦い、という感情を顔で表した。酷い顰め面だ。そういえば彼は甘党だったっけ。「はい」僕が角砂糖の瓶を押しやると、彼は三つもカップに入れた。それでようやく飲めるようになったのか、顰め面がやわらぐ。
その後、彼とは他愛のない話をした。
シリルはいつもの軽くて自由奔放な彼に戻っていたし、なんだかんだで、そんな彼に振り回される日々が少し懐かしく、僕は駅の改札で彼と別れたとき、一抹の寂しさを感じたものだ。
これでしばらくはロンドンの喧騒ともお別れだろう。石畳を踏む感触も、目に眩しいくらいの情報量の立体映像が舞う風景も、人の波も、喫茶店に戻れば夢になる。
「じゃーなー! 電話しろよー!」
駅では、僕が列車に乗り込むそのときまで、シリルが手を振っていた。律儀に、ずっと、列車がセント・パンクラス駅を出るまでずっと、彼は手を振っていた。
5話め! 気がついたら一ヶ月以上たってましたね…。間隔あきすぎ(´・ω・`)
気が向いたらまた書きにきます~
応援! にポチッとしてもらえると励みになります❤(ӦvӦ。)
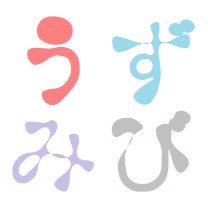






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません