アニリン④
このお話は、DDONのフィンダム大陸に出てくる敵『グリーンガーディアン』と少女を主体にしたお話です!
グリーンガーディアンはこんな魔物です↓

今回で4話めなので、「まだ前の話読んでない!」という方は以下からどうぞ!
まだ何話か続けていく予定です。需要……需要よ~~あれ~~!\( ゚д゚ )/
異臭に気づいた犬は手遅れだったと云う②
あの子と一緒に生活するようになって、一ヶ月。
グリーンガーディアンのあの子は、飽きもせず、捨てもせず、わたしの世話を焼いたので、わたしはまだ生きていた。
あの子と一緒に生活するようになって、二ヶ月。
木の虚で一人と一匹で暮らす。そのことに慣れてきていたけど、ある日、わたしが狼に襲われかけて、あの子が撃退した。
わたしに怪我はなかったけど、居場所が知られてしまった。次に来るときは仲間を連れてくるだろう。それが狼だから。
わたしとあの子は、荷物をまとめて、住み慣れた虚を捨て、野を森を彷徨って、次の家を探した。
あの子と一緒に生活するようになって、半年。
大きな岩と岩の隙間にちょうどいい空間があって、その空間で暮らし始めて、だいぶたった。
昼間、時間が取れれば地道に岩を削っていたから、居住空間は少しずつ広くなっている。
だけど、川が近い。だから、魔物も、動物も、たまに人の声を聞くことがある。ここは水場も近くて暮らしやすいけれど、そのぶん、見つかりやすくもある。
あの子と一緒に生活するようになって、一年。
わたしは生活のため、時折、山や川で採れたものを人里に売りに行った。その度に名前を変え、人柄も偽って、お金ではなく、物々交換での商売をした。そうして手に入るものがわたしには必要だったのだ。
食器。人が育てた薬草。火打ち石。中古だという衣服。針と糸。
様々なものを物々交換しては、必要なものへと変身させた。
薬草は、どうしても苦しくなったときに飲む薬に。
中古でサイズもバラバラの衣服は、着られそうなものはわたしの服に。それ以外は、一度糸を解いて布にしてしまって、それらを縫い合わせて、粗末なりにも布団にしてみた。
ヌイ。リアーヌ。ミーヤ。
偽名を名乗りながら、偽りの笑顔を作りながら、人々に当たり障りなく馴染んでは、その記憶から消えていく。それが、わたし。
川の水で顔を洗っていると、アニリン、と呼ばれた気がして、濡れた顔で振り返った。
わたしの後ろにはグリーンガーディアンのあの子しかいない。あの子は魔物だ。人の言葉は喋れない。……わたしの空耳か。
でも、よかった。
アニリン。わたしの名前。わたし、まだ自分の名前を憶えている。
本名で名乗ることなんてすっかりなくなって、生きるために、偽物の笑顔ばかり上手になって。あの子といるときはいつも表情が抜け落ちた、人形みたいな顔をしているのに。
ぽた、ぽた、と水の落ちる顔に触れる。
顔。そういえば、すっかり、痣も何もなくなった。新しい痣もできない。わたしを殴る人がいないから、傷もできない。……当たり前のこと、か。
「ァ」
「、」
「ぁ、ニ、リ、ん」
拙い、声。聞き取りにくくて、くぐもった、かろうじて声として認識できる音。
口をパクパクさせたり、唸るように牙を見せたりしているのはグリーンガーディアンのあの子だ。「ぅ」とか「ェ」とか声未満の音を口から漏らしながら、喋ろうとしている。わたしを……呼ぼうとしている。
わたしがアニリンだって。この子、憶えていた。ううん、それより。いつの間に人の言葉を。
「しゃべれたの?」
なんだか感慨深くって、わたしの声は滲んでしまった。
アニリン、とわたしを呼ぶ以外、言葉はわからないし、喋れないようだったけど。わたしのことをアニリンと呼ぶだけで、充分だった。充分すぎた。
わたしは苔生した体に抱きついて、片角の頭を撫でた。何度も、何度も。ありがとう、を伝えた。
わたしがアニリンであると、この子は知っている。知っているだけじゃなく、それを、教えてくれる。
グリーンガーディアンのあの子と生きるようになって、三年。
わたしの弱い体は成長とともに少しはマシになって、今では弱ったときくらいしか咳は出なくなった。わたしの病は一時的なもので、永続的なものではなかったのだ。
人なら、わたしの回復を『精霊竜の許し』だとか『精霊竜の奇跡』だとか言うのだろうか。
わたしを救ってくれたのは魔物であるグリーンガーディアン。生を諦めたわたしの世話を焼いた物好きは人ではなく魔物。精霊竜もなにもない。この地に恵みを与えているという竜は、わたしを救いはしなかった。
「アニリン」
「うん」
「オレ、いく」
「じゃあ、わたしはコレね」
根気よく言葉を教え続けて、根気よく勉強し続けて、彼は単語を繋げて喋れるようになった。こんなふうに意思疎通もできるようになった。
弓を叩くわたしに、彼はこっくりと一つ頷いた。
音を立てないように移動を始めた彼を見送って、手作りの弓を構えて、標的である鹿の群れに狙いをつける。
わたしは狩りは上手じゃないんだけど。彼の援護をするくらいならできる。
片方の角しかない彼が茂みから飛び出して鹿を追い始める。狙いは、メスだ。角がないから比較的安全。
だけど群れには当然オスがいて、メスを守ろうと、彼に角を突き出して突進してくる。わたしはそのオスに矢を撃ち込んで追い払ったり弱らせる役だ。
(落ち着いて…もう少し……)
引き絞った弓の的はとにかく大きな部位。胴体。そこめがけて、放つ。
胴体を狙った矢はオス鹿の後肢に突き刺さったようで、オスは悲鳴を上げて野原を転がった。
ラッキーだ。これであのオスは突進はできないだろう。彼の安全が一つ確保された。
もう一頭のオスと角をぶつけ合っている彼の代わりに、逃げ惑うメスの一匹に狙いをつける。
……飛び跳ねて、なかなか、難しい。外してしまった。このままでは逃げられてしまう。
思考を柔軟にして、さっき矢を撃ち込んだオスに標的を変更。当たり前だけど、まだ生きているし、立ち上がろうともがいている。
大して動かない的の左胸めがけて矢を撃ち込む。外した。もう一本。
やがてオス鹿が動かなくなったので、もう一頭のオスと角をぶつけ合って戦っている彼を横目に、オス鹿の角を掴んでズリズリと引きずって運んだ。
標的はメスだったけど、このさい、仕方ない。
オスが群れから欠けると、外から見てそうだとわかるし、あまりしたくはないんだけど。こちらもそろそろ蓄えが少ないから、このさい、選んでいられない。
わたしが充分に距離を取ったのを見て、彼はうまくオスから逃げてきた。わたしが引きずっている鹿の首を咬んでわたしよりも早く引きずっていく。
「今日の狩りは成功だね」
「せいこう」
「メスだったら満点だったけど」
彼の角とわたしの弓を軽くぶつけてお互いを称え合う。
決して楽ではないけど、彼とわたしの生活はうまくいっていた。
住処を変えながら、わたしたちは器用に暮らした。
運悪く人と行き合っても、彼は器用に立ち回った。
あまりにそばにいる場面を見られた場合には、彼がわたしを襲おうとしていた、というふうに芝居してくれたし、わたしもそれに乗った。そして、偽名と笑顔で窮地を救ってくれた人にお礼を言い、別れる。そんなピンチを何度か乗り越えた。
普通の暮らしをしている人にとって、魔物である彼と意思疎通するわたしは、わたしたちは、異端に見えるだろう。だからわたしたちは、多くの人々にとって無難で面倒じゃない道を選んで、禍根を残さない。
わたしと彼は、フィンダム中をさまよううちに、あの場所に戻ってきていた。
そう。あの場所だ。わたしが彼に助けられた、あの場所。
懐かしいような、苦しいような、そんな場所。
「懐かしいね?」
「…なつか、しい、ない」
「懐かしくない、か。たしかに、いい思い出はないよ。でも、ここで君に助けられた。だから今のわたしがいる」
少し高い丘からかつての思い出の場所を見下ろして…道の向こうにあるピクシーのキャンプに目を向けて、わたしは、首を傾げた。
散らかっている。それは、まぁ、相手がピクシーだからというのもあるけど。でも、今まで見てきたピクシーの拠点の中で、今目にしている場所が一番…散らかっている気がする。言い方を変えると、汚い、気がする。不自然な植物も生えている、ような…?
「…何か……変だね」
「へん?」
「変。あそこ」
ピクシーキャンプを指すわたしに、彼は首を捻ってからじっとキャンプの方を見つめた。獣の彼の目の方があの場所もよく見えるだろう。
じっとキャンプを見つめていた彼は、ふんふんと鼻を鳴らして、突然立ち上がった。「どうしたの」「まって、ろ」「え、なんで?」「まってろ」崖を駆け下りていった彼は、ピクシーのキャンプに突っ込んでいった。寝転がっていたピクシーたちがいっせいに起き上がって、いっせいに喚き出す。怖いくらい、まったく同じタイミングで。
彼はピクシーキャンプを一周するようにして走り去って、わたしの視界から消えてしまった。
彼は待ってろと言っていた。戻ってくるんだろう。だからわたしは茂みでじっとしていた。
その間、ピクシーたちを観察した。
彼を追いかけようとして、足で敵わないと知ると、ピクシー全員が同時に動きを止めて、ぎこちなく歩いて、キャンプ地に戻って、寝転がる。その動作が怖いくらい同じだ。
統率が取れた、とは言い難いピクシーが、ここまで同じ動きをするだろうか。さすがに気味が悪い。
早く離れたいな、と思いながらじっとしていると、やっと彼が戻ってきた。
長いこと彼と一緒に生きてきた。だからわかる。彼の表情は沈んでいるようだ。
「アニリン」
「おかえり。なに?」
「しる、か?」
「知る? 何を?」
「むら。おまえ、いる、むら」
…わたしのいた村。エスリグ村? あの村がどうしたというのだろう。
彼に教えた言葉では、彼が表したい表現ができなかったようで、乗れ、と背中を向けられた。
茂みの中に生活に必要な装備を置いたままにしておくのは忍びないけど…。彼がそこまで言うのなら、行ってみようか。
そうして、わたしは見た。
かつての村は荒廃し、建物にあの頃の面影は一つもなく。そこを歩く人からははっきりとした腐臭がした。
頭から何かの胞子を生やしたような、人でないヒトの形を前に、悲鳴を上げなかった自分を褒めてやりたい。
口を押さえたまま動かないわたしに、彼はひっそりと歩き出し、ヒトに見つかる前に村の跡から離れた。
充分に距離が開いたことを確認してから、口に蓋をしていた手をどける。「なに、あれ」…どうやっても震えてしまった。「わかる、ない」彼も、アレが何かはわからないようだ。
でも、知ってる。顔は思い出せなくても、体格と、服装と、持っている武器で、だいたいわかる。あの村にいた人たちだった。わたしが見たのは、人、だったモノ。
どうしてあんなことに。どうしてこんなことに? 一体いつから?
疑問と不安が胸のうちで大きくなっていく…。
それが、フィンダムの変化を知った最初の日のことだ。
やがてその変化は、フィンダムの一部に留まらず、全域を呑み込む災禍となる……。
フィンダムが具体的にいつから侵蝕系の敵に支配され始めたのか? 地域でいうとどの辺りから? など、謎な部分もありながら(ゲーム中で語られてたろうか…?)書き上げました(˘ω˘)
レスタニアのゴブリンが「マヌケ!」とか言うくらいなので、グリーンガーディアンだって練習すればきっと言葉を喋れると思うんだ…! たぶん!!
↑ 続きはこちらからどうぞ
アリスの小説応援! にポチッとしてもらえると励みになります❤(ӦvӦ。)
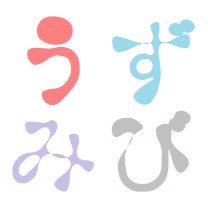



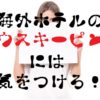


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません